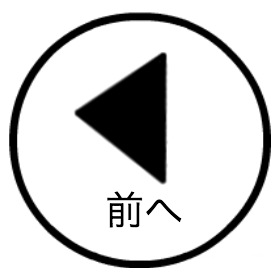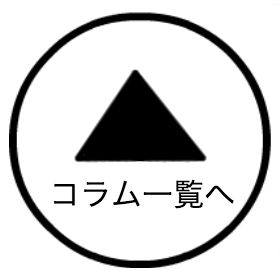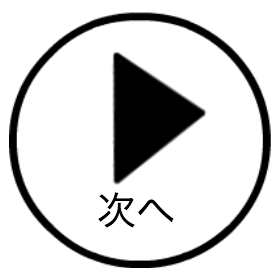元テニス選手の松岡修造は、レストランでメニューを決める際、子どもたちに、10秒の制限時間しか与えていなかったという。
さすが、元アスリート。
一瞬の判断力の過ちが命取りになることをわかっている人の育児である。
判断力はアスリートに限らず、どんな分野でも必要な能力であるため、そのエピソードを聞いて、「うちの子どもにもやらせてみよう」と考える人もいるかもしれない。
しかし、判断力の大切さを自分の身で実感せずに人の家の育児法をなぞっても、うわべだけのものになる。
実感を伴わない育児や教育は元凶のもとである。
松岡修造が「10秒でメニューを決めろ」という時、そこには「問い」がある。
「お前は何を食べるのか」
「お前はどうやって決めるのか」という「問い」。
この「問い」が日本の育児や教育では圧倒的に不足している。
この「問い」は、学校のテストで出題される「問い」とは質的に異なる。
学校のテストやスポーツの試合などで問われるものは、規定のものさしで「できる/できない」を測る試行である。
そこには模範解答があり、評価されるものとされないものが先に決まっている。
しかし、松岡修造が子どもに「問う」時、そこに答えはない。
答えがないものに対して、問う。
松岡修造は、問いに対する答え、答え方、答えの導き方に「個性」が出ることを信じ、問う。
松岡修造が「問う」時、そこにはその子どもの「個」に対する信頼がある。
人は一人ひとり違う。
有機物である限り、具体的に、「必ず」違う生き物である。
その違いがあることを前提に「問い」が生まれ、その答えによって、各々の「違い」は明確になる。
「問い」は、絶対に存在する、その子ども(=個)が持つユニークな性質を取り出すためのものである。
その意味で、「問う」ことは人としての信頼の証である。
それは、自分の理想を押し付ける「期待」とは違う。
「問う」人は、自分が望む答えを期待しているのではなく、返ってくる「答え」が自分の想像を超えることを期待している。
そして、人が一人ひとり違う以上、必ずオリジナリティの源泉を皆持っているのだと信じている。
つまり、人は元来ユニークでありオリジナルである存在だということを前提として、「問い」は発せられる。
たとえ、返ってきた「答え」が的外れであっても、「気弱さ」や「わがままさ」のようなネガティブな性質を表すものであっても、そこにユニークさ(=その人であるということ)があることを認める。
そこでいうユニークさとは、「秀逸さ」や「稀有さ」ではない。
誰かと違っていたり、周りより秀でていることがユニークさではない。
ただ、その人がその人として生きていることが他の人に取って代わられないという、まざまざとした事実のことである。
松岡修造が「10秒でメニューを決めろ」という時、それは判断力の訓練だけをやっているわけではない。
彼は、子どもに「問うて」いるのだ。
「誰にも取って代わられないお前とは一体、誰だ」と。
それは、子どもからすれば、親にとって自分が唯一無二の存在なのだと理解する「問い」である。
目の前の大人がいつもこっちに目を向けてくれている、そして、未来への期待ではなく現在への全幅的な信頼のもとに聞いてきているという、「大安心の問いかけ」である。
「大安心の問いかけ」があれば、周りの人間と比べて、意識的に「自分らしく」あろうとしたり、無理に、「個性」を発揮したりする必要がない。
本当のユニークさとは、「自分を超えたユニークさ」である。
自分が意識する前にすでにあるものであり、この社会での評価を超えたものである。
だから、その子のユニークさは、現世的には大したことないかもしれないし、逸脱したものかもしれないし、批判され得るものかもしれないが、それは一旦それとして、まずは、そこに元来からあった(=あってしまった)性質を認めるというのが、松岡修造の姿勢であり、親の姿勢である。
これがレストランでなく、学校や習い事や仕事場において見られれば、それは教育者の姿勢である。
親や教育の側に立つ大人がまずすべきことは、「子どもに正解を教えること」や「子どもに期待すること」ではなく、大人が子どもに興味を持っていることを示すことである。
その現れの一つが、「問い」という形である。
「10秒ルール」によって、松岡修造の子どもは食べたいものが食べられなかったかもしれないが、その「問い」によって潜在的に得られる「大安心」に比べれば、その損失は大したことではない。
食べたいものはいつでも食べられるが、「大安心」はいつでも手に入るものではない。