
「大切なものは目には見えない」と言ったのは、
「星の王子さま」というかサン=テグジュペリだけど、
そのことを大人はほんとうに理解できるのだろうかと考える。
先日、高校生が、先生に怒られていた。
「家での学習時間が少ない」とのことで、
「毎日あと2時間は、やれ」とのことだった。
親が子どもに「勉強しろ」という回数と子どもの成績の良さはきれいに反比例すると、
小学生を対象にしたデータが示している。
大人は子どもが勉強しないからこそ「勉強しろ」と言うのだが、
「勉強しろ」と言うたびに子どもは勉強しなくなるというジレンマ。
それは、小学生でも高校生でも、親でも先生でも同じこと。
「もっと勉強しろ」と言ってやるような高校生は、
言われる前にすでにやっている。
大人は、日常を生きていて、目に見えるものを問題にしたがるので、
「学習時間」や「偏差値」など、目に見える数字を見て、
「あと2時間やれ」「あと20点足りない」と言う。
子どもは、大人ほど「目」が見えていないので、
目で見えない部分を、「想像」で補って生きている。
精神科医や心理学者の本には、
夢での出会いや動物との別れが子どもを大きく変えた実例が紹介される。
現実に疎外感を感じて、犬を飼いたいと思っていた男の子が、
「絵」の中の犬と交流することで、だんだんと変化していく。
また、家の外では一言も言葉を発しなかった少年が、
亀を飼育することで、じょじょに声を取り戻していく。
はためには、ただの「絵」や「亀」であっても、
当人は、そこに大きな「意味」や「物語」を見出している。
子どもが「声を出せない」という問題を持っている場合、
まわりの大人は、それが「声帯」の問題ではなく
「精神」の問題だとわかるので、
強制的に声を出させようとはせず、自発を促すきっかけを待つ。
しかし、勉強の話になると、
大人は、それを「精神」の問題だと思わず、「やる気」の問題にして、
「怠惰だ」「怠けている」と叱りつける。
しかし、それが「精神」の問題ならば、「目の前」に問題の核はない。
大人に対して反感を持っている子が、
学歴社会に入るための勉強を進んでしないように、
親からの愛情に飢えている子が、勉強よりも人間関係を優先させるように、
勉強しない子は、勉強以外の部分に問題を抱えている。
それは、「目には見えない」問題。
それを放置したままで、勉強をさらに2時間やらせても、あまり意味がない。
問題を「目に見える部分」だけで解決しようと考えている限り、
状況がよくなることは望めない。
大人でさえ、恋愛が上手くいきはじめると、
仕事も上手く回るようになるということが普通にある。
恋愛は「思い込み」の最たるもので、
頭の中で想像したもので「現実」を補完する。
大人でも、そういったものが、現実の効率を上げるならば、
想像の中で生きている子どもならなおさらだ。
だいたいの問題は、「目に見えない」ところにある。
大学時代、友達との交換条件で、
「星の王子さま」についてのレポートを、代筆した。
4000字のレポートはとりあえず書き上げたが、
サン=テグジュペリがなにを言いたいのかは、ぜんぜんわからなかった。
20歳では、「大切なものは目には見えないんだよ」ということが
もうわからなくなっている。
たぶん、そのことがちゃんとわかるのは
「子ども」と「じいさんばあさん」で、
子どもは「もちろんそうだよ」と同意し、
老人は「やっぱりそうだな」と再認識する。
その、子どもとじいさんばあさんの間にいるほとんどの大人は、
そのことには気づけない。
だから、せめて、大人は、「大切なものは目に見えない」ということがわからない
ということを自覚しておいた方がいいと思う。
ただ、「こども」や「じいさんばあさん」というのは、
「精神」のことを指しているので、
大人の中にも、「星の王子さま」を理解できる人はたくさんいるのだとも思う。

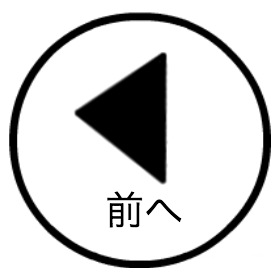
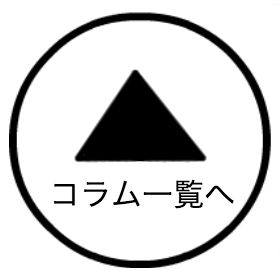
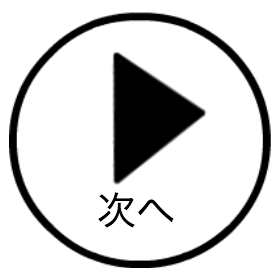
コメント