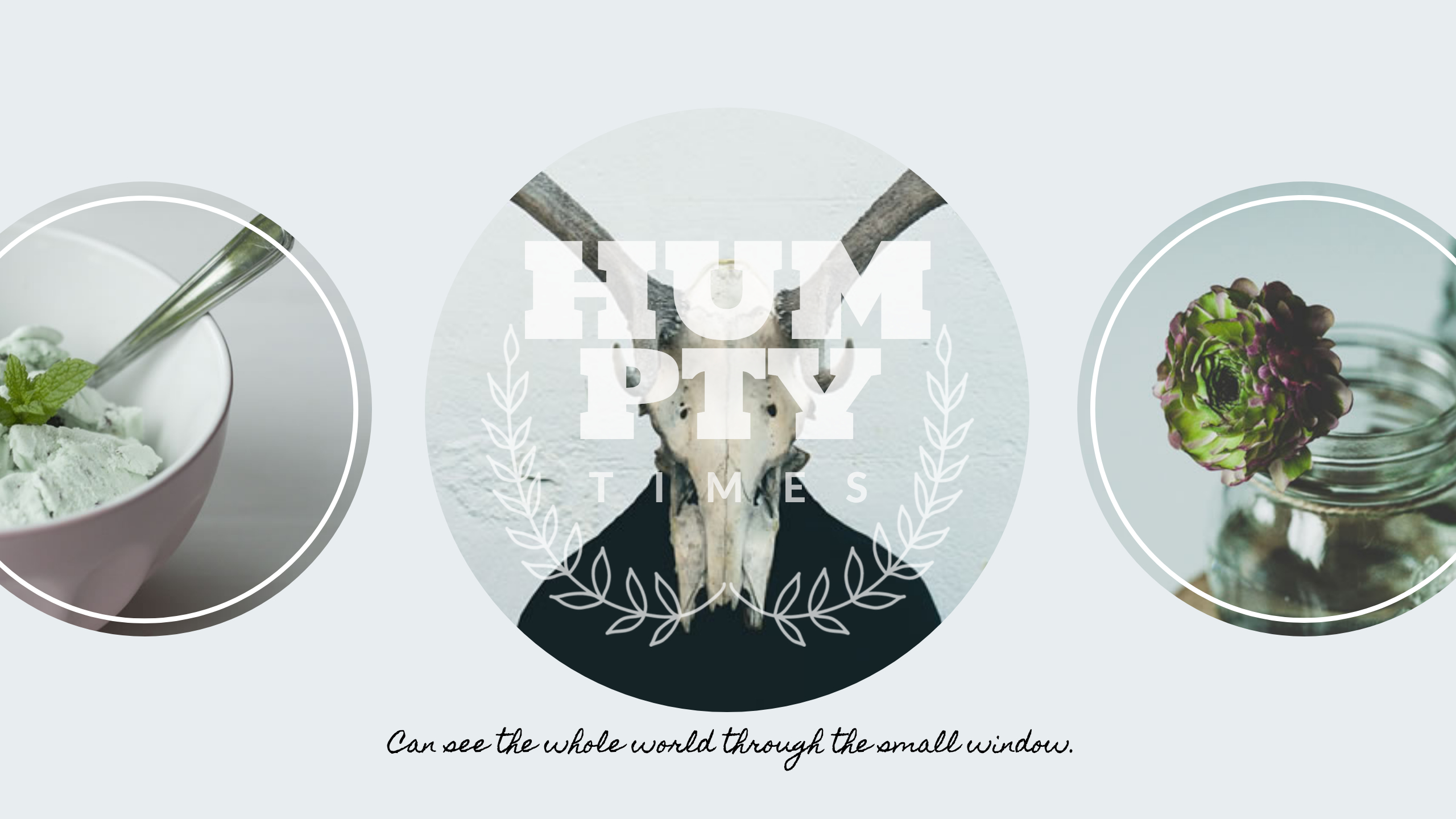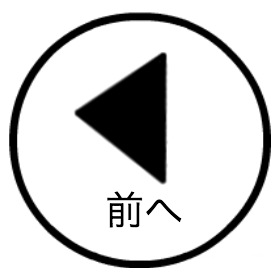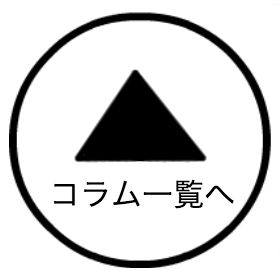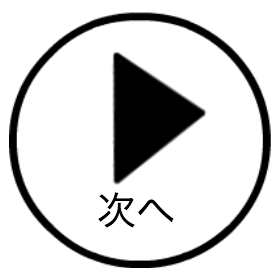泥棒のはなし。
良寛という和尚さんは、自分の家に泥棒が入った際、あまりに質素な生活なので何も盗むものがない泥棒のために、わざと寝返りを打ち、布団を盗みやすくしてあげたというエピソードがある。
名僧は、盗まれる側になっても、盗む側のことを考えてあげている。
エジプトのサッカー選手であるモハメド・サラーは、自分の家に強盗が入った際、その強盗を捕まえはしたが、警察に突き出すのではなく、その強盗に仕事を探してやったというエピソードがある。
自分が持っている価値あるものをあげるのではなく、その人がこれからも生きていけるように仕事を探してあげるというのは、「賢人は魚をあげるのではなく、魚の釣り方を教えてあげる」という金言を思い出させる。
批評家の小林秀雄は、家に泥棒が入った際、その泥棒からほっぺたに短刀をつきつけられ、「起きろ」と凄まれたが、「ちょっとタバコを吸わせろ」と言って、一服しながら、その泥棒に説教を始めた。
小林が、滔々と諭すと、段々、泥棒も本意を翻して退散し、後日、菓子折りを持って小林に礼を言いに来たという。
良寛も、サラーも、小林秀雄も、三者三様に自分が持っている有形無形の財産を泥棒に与えた。
彼らのとっての「自分の物」は、余人にとって程「自分の物」ではなく、手の中に握りしめるほど大切なものでもなかったのだろうと推測する。
欲しければあげるよ。
小林秀雄には、また別の、泥棒に関する話がある。
とある大学の教授の家に泥棒が入った際、その教授は泥棒を床の下から隠れつつ見ていたのだが、泥棒が有り金全部を持って去るという段になって、教授はたまらず、「お前ら全員の顔を見たからな!」と叫んだ。
すると、その泥棒たちが引き返してきて、その教授を殺してしまったのだという。
小林秀雄はこれを、(大学教授が持っていたであろう)知識と、(大学教授に欠けていた)心(=大和魂)の例として書いているのだが、まぁ、ここで「大和魂」と言うと話がどこかにいっちゃいそうなので置いておいくとしても、小林秀雄が指摘したいのは、知識と精神の乖離であり、小林は、その乖離がないことを、自分の体験で証明したことになる。
戦後の日本を描いた黒澤明の作品『どですかでん』の中にも、家に押し入った泥棒に金品の在り処を教えるおじいさんが出てくる。
寝ぼけたじいさんに、お金が入っている場所を教えられた泥棒は、戸惑いながらも金をもらっていく。
その泥棒の、「え、教えてもらっていいんですか?あ、ありがとうごぜえます」といった姿勢を見ていると、泥棒に入られた側が泥棒を許す心を持つためには、泥棒の側にも「可愛げ」がなければならないのかもしれないと思う。
今、テレビで、家に押し入られて金品を盗られたという類のニュースを耳にすると、「泥棒」というよりも「強盗」と呼んだほうがいいようなリアリスティックなニュアンスがあり、そこに「可愛げ」が入る余地はない。
現代は、相当に「現実的」で、ものを盗る側、盗られる側、双方に余裕がない時代なのかもしれない。
良寛和尚は、布団からずれて、泥棒に布団を盗ませてあげた後、
「盗人に取り残されし窓の月」
と、詩を詠んだという。
泥棒に入られて詠む詩。
それは盗る側も盗られる側も牧歌的な時代にこそ詠めた詩であろう。
(まぁ、良寛和尚くらいなら、現代に強盗されても詩を詠むかもしれないけどね)