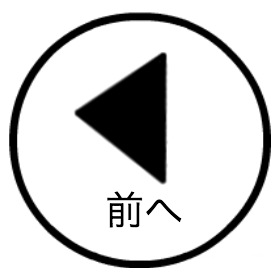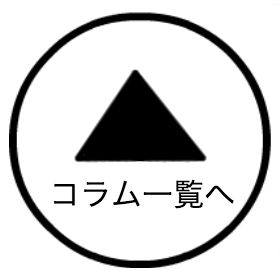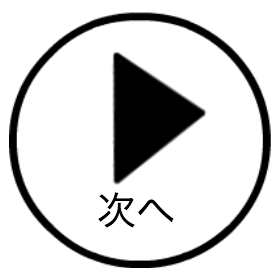「音楽」の授業で歌った歌は今でも覚えているが、「国語」の授業で扱った小説は一つも覚えていない。
それは、国語の教科書に載っている小説がつまらないのではなく、教科書に載ることで小説がつまらなく感じてしまうからだろう。
どんなに良い小説でも詩でも短歌でも、国語の授業内で読むと、途端につまらなくなる。
勉強やスポーツを強制されるより自主的にやったほうが成績が伸びるように、本を読むことだって、強制されるより自主的に読んだほうが自分の中に入ってくるはずなのに、国語の授業は、なぜか、クラスの皆と歩調を合わせながら読まされる。
100メートルを6秒で走れる人が、9秒でしか走れない人たちと同列で並んで走らされたら、それは苦痛でしかない。
自分のペースじゃないのに、楽しいわけがない。
国語の授業で扱う小説や随筆や詩は、文学作品であり、芸術作品である。
「美術」の授業であれば、絵画や彫刻などの芸術作品を生徒に見せて、その作品をどう見るべきかという、「正解」の見方を生徒に押し付けるようなことはしない。
作品を見た時の感じ方は人ぞれぞれ。
感性は押し付けることができないと考える。
それなのに、国語の授業では、文学作品の正しい読み方があるかのような、細かい読み方の解説が続く。
小説に出てくる登場人物の振る舞い方に対する「感じ方」は読む人それぞれの感性による、とはならない。
ただ、問題は、「美術」に対する子どもたちの「好き・嫌い」は、学年が上がるにつれ悪くなることだ。
つまり、学年があがることに、「美術が嫌い」という子どもが増えていくのだ。
「感じ方は人それぞれ」という、子どもに「正解」を与えず、自分の中の「正解」を取り出させようとするアプローチは、だんだんと嫌われていく。
ここが、クラスで一斉授業をすることの難しさであろう。
クラス全員で足並みを揃えて作品を読もうとすると、「つまらない」と思う子がいて、それぞれの感じ方に委ねて作品を鑑賞しようとすると、どう感じてよいかわからずに嫌いになる子が増える。
得意な子にはのびのびと先に進ませ、不得意な人には丁寧にフォローする。
理想はそうだが、現実には困難さがつきまとう。
「言うはやすし・きよし」である。