
TEDというプレゼンテーション団体がある。
「広める価値のある考え」をモットーに、
観客に囲まれ、壇上に立ったプレゼンテーターが、様々な考えを発表していく。
そのフォーマットは世界中で知られるようになり、
NHKでも専門番組があり、
TED×Kyoto、TED×Tokyoなど、日本各地でも会が開催されているのだが、
このプレゼンの形式は、スタンダップコメディの国の形式だなぁと、いつも感じる。
観客の前で、身振り手振りを交えて、
適度に観客をいじりながら、一人で話を進めていく。
これまで日本人もたくさん登壇しているけど、
あの形式がしっくり来ている人がいるのだろうか、と思う。
みんな、探り探りやっているような印象を受ける。
スタンダップコメディ形式は、スピーチの文化がある国の形式だ。
福沢諭吉は早い段階から日本でもスピーチの文化を育てようとしたようだが、
あまり上手くはいかなかった。
日本はスタンダップコメディの国ではないのだから、
日本でTEDをやる際は、
一人じゃなくて二人でプレゼンテーションした方がいいんじゃないかとも思う。
漫才にしても、バラエティ番組にしても、
トークだけで何かを説明したり客に納得させる時は、
一人よりも二人の方が上手くいくのが日本スタイルだ。
メインMCの隣にいるアシスタントというのは日本でよく機能しているし、
女子アナという日本で花開いたアシスタント文化もある。
テレビショッピングで商品を説明する際も、
一人で商品の良さを説明するよりも、
隣のアシスタントが、合いの手や決まったフレーズを連呼することで、
プレゼンに、いいリズムが生まれている。
TEDのモットーは、「広げる価値のある考え」だが、
一番広がっているのは、「考え」ではなくあの「形式」だろう。
ただ、あの「形式」にうまく乗る「考え」もあるし、
うまく乗らない「考え」もある。
形式は常に、内容を規定する。
非欧米国は、あの「形式」にうまく乗らない「考え」を乗せる「形式」を、
そろそろ考えたほうがいいのかもしれない。
TEDのようなプレゼンパッケージは、
アメリカならどこにでも似たようなものが転がってそうなものだが、
そうではないようで、TEDの創業者は、
イギリス人の起業家に、
15年前にTEDを売却している。
TEDはれっきとした商品なのだ。
発表形式を商品にして売却するという、その姿勢がまさにアメリカンで、
「形式」同様、感覚の違いを感じる。
非欧米国、日本はそろそろ、日本の発表方法を考える時期かもしれない。
日本にはまだ世界にしられていない「形式」があると聞く。
「RAKUGO」という形式もあるというし、
「HINADAN」という形式もあると聞く。
「伝え方」を変えることで、まだ伝わっていないことを伝えることはできるはずだ。

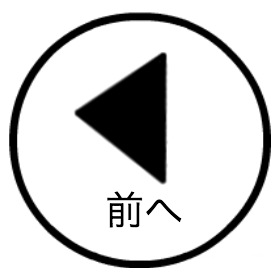
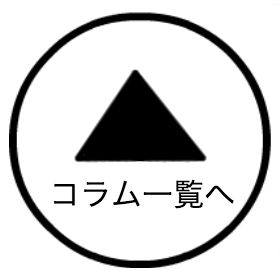
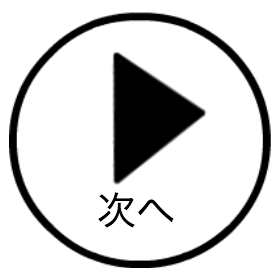
コメント