
”自主性”という言葉がある。
教育の現場でよく聞くこの言葉は、
だいたいにおいてプラスのイメージで使われるが、
なんだか、いいように利用されているなと思うことも多い。
日本の学校教育はずっと「詰め込み」や「暗記中心」と批判されてきたので、
「自主性を重んじる教育」は、昨今、とても歓迎される。
もちろん子どもに自主性があれば好ましいし、
自分の意志を持たない子どもたちは困ったものだと思うけれど
自主性って、ほんとに子どもから”自主的に”生まれてくるのかなと
常々、疑問に思っている。
自主性を重んじる教育では、
「これがやりたい」「こういう風にやりたい」という
子どもたちの意思や思いを尊重しなければならないが、
まだ十数年しか生きていない子どもは、
好きになるものの幅も、興味を持つ分野も、けっこう狭い。
「よくわかんないけど、ちょっと面白いかも」と思うよりも、
「よくわかんないから嫌」「そんなこと別にしたくない」と
初めてみるものを否定することの方が多かったりする。
子どもってけっこう、保守的なのだ。
そんな保守性のある子どもの”自主性”を重んじようとすると、
子どもは、どんどん、自分の手の届く範囲のことしかやろうとしなくなる。
子どもたちのプロジェクト発表なんかを聞いていても、
「発表する時の自分」が、
「最初にアイデアを思いついた頃の自分」を超えていないことがほとんど。
過去の自分が考えついたことを、
未来の自分が上手く証明したとしても、
そこにどれほどの価値があるだろう。
十代の子どもが予想できる範囲内で色々動いたとして、
そこに、どれほどの成長があるのだろう。
『声に出して読みたい日本語』などで有名な教育者の齋藤孝氏は、
以前から、「漢字の総ルビ化」を提唱していて、
すべての漢字にルビをふるべきだと言っていた。
日本は以前、新聞などの刊行物にはすべてに漢字にルビがふられていて、
子どもでも、大人の読み物を(内容は分からないくても)読むことはできたのだが、
常用漢字が決まってからか、
常用漢字以外の漢字にルビがふられなくなり、
子どもは、大人の本に手を出しにくくなった。
すべての漢字にルビがふられていれば、
どんなに難しい漢字を使った本であっても、
(意味はわからないくとも)読むことだけはできる。
理解できなくても、読めさえすれば、その本を感じることができ、
その本が持っている息遣いのようなものを体感することができる。
大人が読む難しい本や名著に子どもが触れる体験は、
未知なる世界の一端に触れるチャンス。
「3年生は3年生で習う漢字が使われている本だけ読んでいればいい」
そういう考え方は、子どもの背伸びを邪魔をしている。
「なんだかわからないけど、触れてみる」
それは、成長の第一歩。
自分の手に届きそうなものだけで満足していると
成長は、予想を超えていかない。
理解できなくても、自分の実力を超えたものに触れることで
人は、予想を超えて成長していく。
「子どもには無限の可能性がある」などと大人たちは言うが、
子どもはこれからどうなっていくかわからないから希望があるのであって、
保守的に判断したがる子どもの”自主性”に委ねて、
自分の範囲内のことにしか手を伸ばさなくなったら、
子どもには、想定内の、「有限の可能性」しか残らなくなる。
自主性は悪いことではないが、
「子どもの自主性を重んじる」よりは、
「子どもの自主性を育んでやる」方が大事かと思う。
子どもはやりたいことは勝手にやるのだから、
「子どもがやりたいかどうか判断もできないこと」をさせて、
子どもの幅を外から広げておいてやることが、
子どもが今後、本当に自主性を発揮しなければいいけない場に立った時に
大切なことかなと思う。

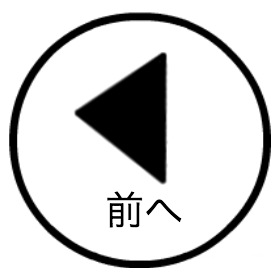
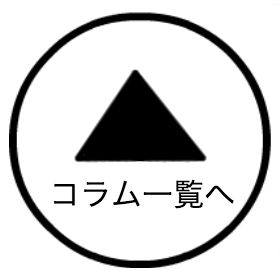
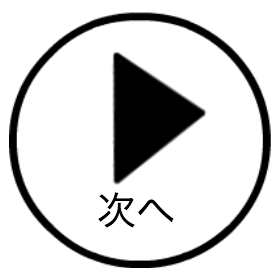
コメント