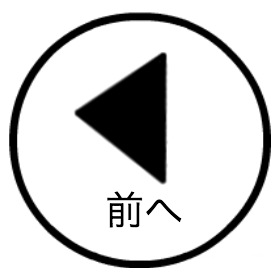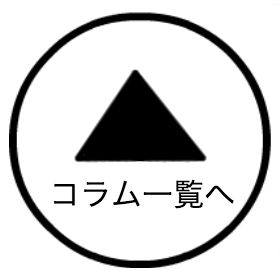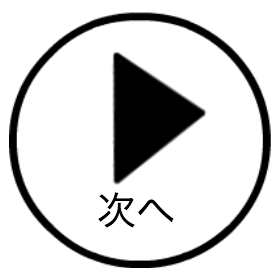先日、会話の中で、ある女性が、
「”嫁”っていうのは、”家の女”って書くからダメ。
”奥さん”っていうのも、”奥にいる人”ってことだからダメ。
”家内”なんて、”家の内”だから、もってのほか。
”女房”も、昔の使用人の意味だから、もちろんダメ。
だから、パートナーの呼び名は、”妻”しかないわよね」
と言っていて、
僕は、「”妻”って、刺し身のツマみたいな、”添え物”って意味もあるけどいいのかなあ」
と思いながらも、
「なるほどですねえ」と、空虚な相槌を打って頷いた。
婚姻相手の女性を呼ぶ名称は様々にあって、
それぞれの立場や状況によって正しい呼び方があるらしいが、
一つひとつの言葉にあまり目くじらを立ててもしょうがないのではないかと思う。
言葉は常に変容しながら使われているので、
言葉の「正しさ」や「由来」をどれだけ正確に追求しても、
何の色も付いていない真っ白な言葉なんかなくて、
どの言葉も、歴史的、慣習的に、何かしら、時代的な色を背負っている。
例えば、最近の若い人は、当たり前のように「全然楽しい」と、
「全然」を、<肯定表現>として使うが、
その使用法に違和感を覚える世代はたくさんいる。
彼らは、「『全然』を肯定表現で使うのは間違っている」
と、若者の間違いを指摘するが、
夏目漱石や森鴎外など、明治時代の文学では、
「全然正しい」「全然おいしい」と、
「全然」を<肯定表現>として使っていて、
由来的には、「全然」を<肯定表現>で使うのは間違いではないとされている。
時代によって、言葉は使われ方が変化するもので、
文法的、由来的に正しかった言葉も、なんだか変に聞こえてきたり、
以前はしっくりハマらなかった表現が、違和感なく聞けるようになったりする。
言葉は、それほど固定しているものではない。
婚姻した女性を呼ぶ名称も、時代ごとに、
受ける印象やイメージは変化しているが、
もし、冒頭の女性に、
「私は普段、妻のことを『かみさん』って呼んでます」と言ったら、
彼女は、なんと言っただろうか。
「かみさん」の持つ、粗暴で女性を軽視した言葉の響きに、
「なんですとぉ!」と怒りをあらわにしただろうか。
今の若い人はあまり伴侶のことを「かみさん」とは言わないが、
「かみさん」とは「おかみさん(女将さん)」のことで、
女主人などに対する「敬称」として使われていた言葉だ。
その「女将さん」は、もともと「お上様(=上様)」なわけで、
相手に敬意を表する、丁寧な呼び名だったはず。
音としても、「神様」に通じるし、由来的には、
どこにも女性に対する非礼がない言葉だろう。
しかし、この現代に、「うちのかみさんがさぁ」と、
パートナーを「かみさん」呼ばわりする若者がいたら、
その男は、ジェンダー意識の薄い、権威主義的な男だと思われるだろう。
「うちのかみさんがさぁ」と話す男が、
奥さんのことを、「内の神様=家族の守り神」だと思って話していたとしても、
粗暴な言葉の響きだけで、その男は、女性軽視の烙印を押される可能性がある。
ポリティカル・コレクトネス(政治的妥当性)的には、
「かみさん」は間違っていて、
「妻」が正しい呼び名なのかもしれないが、
当人の、サイコロジカル・コレクトネス(心理的妥当性)や
ミューチュアル・コレクトネス(相互間妥当性)的には、
「かみさん」が正解な人たちもいるだろう。
日本語は、「ポリティカル・コレクトネス」が叫ばれている欧米の言葉よりも、
立場や状況によって使う単語が変化する言語だ。
「ポリティカル・コレクトネス」の必要性はもちろん感じるが、
立場や文脈や関係性を抜きにして言葉の正しさ(コレクトネス)を語ることには、
どれほどの意味があるのか、考えてしまう。