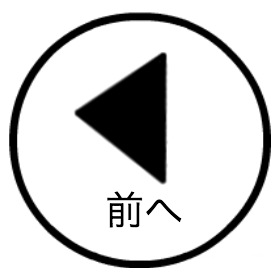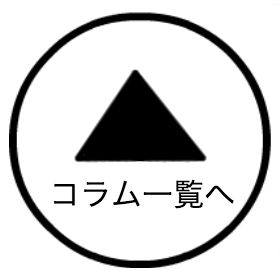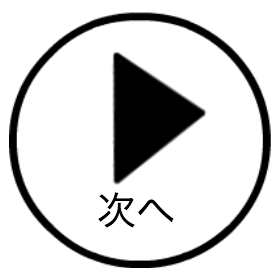チャールズ・ディケンズの「クリスマス・キャロル」を読んだ。
「クリスマス・キャロル」といえば稲垣潤一という我が国では
ピンとこない人もいるかもしれないが、
「クリスマス・キャロル」といえば、チャールズ・ディケンズであり、
「チャールズ」といえば、チャップリン、皇太子、マンソンに続いて、ディケンズなのだ。
「クリスマス・キャロル」は1843年に送り出されたクリスマスを舞台とした名作。
金に強欲なじいさんが、3人の幽霊に連れられて自身の過去のクリスマスと
現在の各家庭のクリスマス、
そして、未来のクリスマスを見せられることで改心するという話。
現在の感覚からすると、少々、単純すぎるストーリーにも思えるが、
名作とは常にまっすぐさを兼ね備えているものだろう。
作品には、産業革命が起こり、資本家と労働者との格差が広がった都市部で、
どういうクリスマスが迎えられたかが伺い知れるが、
それでも、1830年代というのはキリスト教の影響がまだ強く、
生活の中に資本主義の波が押し寄せてきていない。
作品内でクリスマスを祝い喜ぶ人たちも、
家庭での食事を楽しんだり、家族で教会や礼拝堂に行くことが主で、
現在のようにプレゼントを購入したり、
どこかのレストランに特別出かけたりするようなことはしない。
当時の楽しみは主として食べ物で、
ハレの日にだけ特別食べられる七面鳥や牡蠣、豚の塩漬け、パイやプディングなどがごちそうだった。
以前、1900年代初頭の日本の正月のごちそうを並べた本を読んだことがあるが、
あれが本当なら、1830年のイギリスのクリスマスは、
100年後の日本の正月より、断然裕福だと思わされる。
1900年の日本人は鯛一匹で大喜びしていた。
作品中のクリスマスは、キリスト教の祝祭という点も色濃い。
主人公のスクルージの甥が言うように、クリスマスによって、
人を赦し、情深くなって、
他人を”赤の他人”だとは思わなくなる感覚がまだあったと思われる。
クリスマスを皆で祝うことによって、皆が同じ墓場に向かう仲間だと思える感覚。
その人間同士の仲間意識は現代ではさらに薄くなり、
「クリスマス商戦」という言葉が表わすように、
クリスマスはただの購買イベントになりさがっている。
それは非キリスト教圏である日本に限らず、欧米各国でも同じことだろう。
かつて、日本の正月や豊穣を祝うための秋の祭りが、
コミュニティメンバーの結束力を高めると同時に、
メンバー全員に対する慶事だったように、
季節の行事は、他人に対する寛容や慈しみを育む機会でもあった。
産業革命が花開いたヴィクトリア朝にこの作品を書いたディケンズは、
進行する工業化や都市化によって助長される、人々の断絶を肌身に感じていただろう。
それまで小さなまちの祭りや催しが、
コミュニティの結束に役立っていたのに比べ、
産業革命後によって生じた大都市では、
まち全体をまとめる催しが機能しなくなっていたと思われる。
金を稼ぐことや物質的に豊かになることが肯定され、
他人への慈悲心を持つ余裕がなくなった時代において、
クリスマスは、最も他人に寛容になれる機会だったのではないだろうか。
だからこそディケンズは民衆に支持された。
ただ、元々キリスト教へのルーツを持たない日本では
「ディケンズのクリスマス」に還ることはできない。
今のクリスマスから、クリスマス商戦とカップルたちのための
イルミネーションとケンタッキーフライドチキンを除いたら、
何も残らない。
元々精神を抜いて形だけ輸入したものに期待することはできない。
還るべきは「ディケンズのクリスマス」ではなく、かつての日本の季節行事だろう。
日本の行事にはかつてはなんらかの精神が宿っていたはず。
現在、日本各地で行われている祭りが、
観光客を呼ぶためのイベントではなく、
他人への寛容や慈悲心を育むための催しになってほしい。
3人(匹?)の幽霊によって、
過去と現在と未来をまざまざと見せつけられた強欲じいさん・スクルージは、
物語の最後に改心し、人々のために尽くすようになる。
そして、まちの人々に「スクルージは、最もクリスマスの祝い方を知っている人物」
だと褒め称えられる。
「クリスマスに多額のチャリティをしてくれる人」や「巨大なパーティーを開く人」ではなく、「クリスマスの祝い方を知っている者」が、最上の褒め言葉になるのだ。
現在の日本で、正月やクリスマスに高価なプレゼントを買える人間が
どれだけ褒められているかは知らないが、
それよりも、正月やクリスマスの祝い方を知っている者が
尊敬される世の中であってほしいほんだなぁと思う。