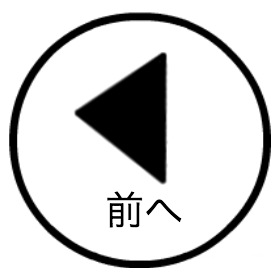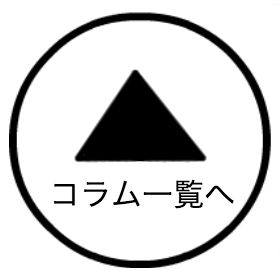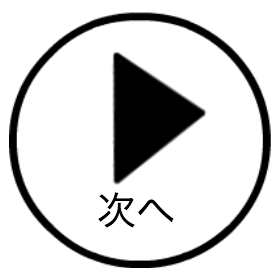作家の坪内祐三さんが死んだ。
坪内さんの作品はほとんど読んだことがなかったが、
多大な影響を受けた同僚がその死にショックを受けたようで
「追悼したい」というので、飲みにいくことになった。
たいして著作を読んだこともない人で、
しかも、会ったこともない人の追悼っていうのは、
なにをするものなんだろうかと思ったが、
同僚が坪内祐三さんにまつわる個人的な昔話を話し始めたので、
相槌代わりに、関係ありそうな、別の作家の話をしていればいいようだった。
しかし、同僚が坪内祐三さんの話をしていたのは最初の15分だけで、
その後は違う作家の話ばかりしていたので、
もしかしたら、あいつは、ただ酒が飲みたかっただけなのかもしれない。
自分の私淑・敬愛する人が死んでしまうと、大きな喪失感を感じざるをえない。
もうこの世に生きていない人は、
新しく文章を書いたり、自分の考えを表明したりしない。
新しい問題が起きても、世の中が変化していっても、
それについてなにかを教えてくれる人はおらず、
自分で考えるしかないという事実に気づくと、
心細く、不安で、寂しい。
坪内祐三さんを追悼したつもりの酒宴が終わり、
家に帰ってからもなかなか寝付けなかったので、
かばんの中にあった向田邦子の『夜中の薔薇』を読んだ。
坪内祐三さんは61歳での急死だったそうだが、
向田邦子も飛行機事故での急死だった。
51歳だった。
彼女も急死だったが、生前、大きな病気を患っていたために、
文章の中に、死の気配がちらほら見え隠れしている。
51歳という、死にはまだ遠く感じる年齢で、
しかも、直木賞を受賞してまだ間もない、
これからという時であったはずなのに、
なんだか終わりの静けさが行間から漂っている。
その文庫版のあとがきで、向田邦子を敬愛する爆笑問題の太田光は、
自身が向田邦子から受けた影響を並べた後、
人間のことをたくさん文章として残した彼女を「黙っていた人だった」と書く。
数々の脚本やエッセイ、小説を書いた向田は、
数としてはたくさんの文章を残したが、
その文章は「黙ること」の必要性を語るものだった。
小説でもエッセイでも、彼女の作品に登場する人たちは、
説明したり、主張したり、懇願したりするよりも、
押し黙ったり、反芻したり、内省したりしていた。
そんな向田邦子が、簡単に意見を世界に表明できる現代社会に生きていたら、
どう振る舞うのだろう。
誰もがすぐに言葉に反応して反射的に言葉を投げ返す世界で、
どう軽やかに生きれただろうと、太田は想像する。
言葉をつかって「黙る」ことを伝える人は、
インターネットの中で誰もがぺらぺら「しゃべっている」人たちの中で、
颯爽と生きれただろうか。
それとも、他の多くの作家同様、
「黙る言葉」は、お手軽に吐かれた軽い言葉の波に沈んでいっただろうか。
文庫版の表に描かれた自画像にも似た猫に無言で、そう問いかける。
詩人・茨木のり子は、詩集『みずうみ』の中で、
「だいたいお母さんはさ、しいんとしたとこがなくちゃいけないんだ」
という小学生の女の子のセリフを引用し、
「お母さんだけとは限らない
人間は誰でもこころの底に
しいんと静かな湖を持つべきなのだ」
と続ける。
向田邦子はしいんとした湖を言葉によって表現した人で、
この言葉は、多くの湖を持つ人や、湖を忘れかけていた人たちに届いた。
その向田邦子も今では死人となり、この世にはいない。
死後の世界は、どんな場所だろうか。
しいんとしているだろうか。
写真家の藤原新也は「眠りは死の練習」と言ったが、
「眠りが死の練習」であるならば、
生きている間に、喧騒から距離を置いて、
ひとり、心の奥の、静かな湖のほとりで佇み、黙っていることも、
死後の世界に生きるための練習なのだろう。
生きながらしいんと生きていた人たちの文章は、
死んだ後も、同じようにしいんとした音を響かせている。
僕を誘って追悼と称して酒を飲み、家に帰った同僚は、眠りに付く前に、
敬愛する人の本をめくれただろうか。
酒を飲んで死者のことを語ったことや、死者の残した文章を読み直すことが
追悼になるかどうか確信はないが、
生きているものの慰めになることは確かだ。
いまは、ただ黙って、湖のほとりで、死者の本を読む。