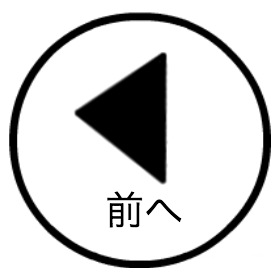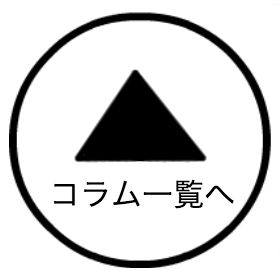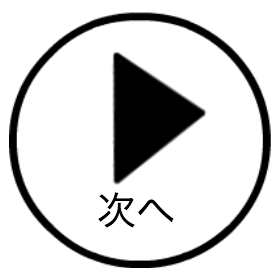私達が別れの際に使う「さようなら」は、もともと「左様なら」であり、
「そうならねばならぬのならば」という諦めの言葉だ。
作家の須賀敦子は「遠い朝の本たち」で
世界的飛行家チャールズ・リンドバーグの妻アンの言葉をこう紹介する。
さようなら、とこの国の人々が別れにさいして口にのぼせる言葉は、もともと「そうならねばならぬのなら」という意味だとそのとき私は教えられた。「そうならねばならぬのなら」。なんという美しいあきらめの表現だろう。西洋の伝統の中では、多かれ少なかれ、神が別れの周辺にいて人々をまもっている。英語のグッドバイは、神がなんじとともにあれ、だろうし、フランス語のアディユも、神のみもとでの再会を期している。それなのに、この国の人々は、別れにのぞんで、そうならねばならぬのなら、とあきらめの言葉を口にするのだ
この国の人は、出会いも別れも、ちゃんと受け入れる。
「左様なら」、「そうであるならば」、とその「運命」を受け入れる。
その姿勢は、「この一度きりだ」「次はないかもしれないよ」
と教える「一期一会」の考え方にも通じる。
出会いも別れも「運命(もしくは縁起)」として受け入れようとする姿勢が
「一期一会」なのだとしたら、
遠く離れても連絡が取れるようになり、実質的な「サヨナラ」が少なくなった現代人に、
その言葉がどれだけ理解できるのだろうか。
卒業か 縁があればまた会おう自信がなければLINEを交わそう
卒業にまつわるそういう短歌がある。
(あるというか、僕がつくった)。
縁に頼らず、メッセージアプリに頼る現代人は、
「卒業」であっても、サヨナラをしない。
実質的な「サヨナラ」をしなくなった私たちは、
「左様なら」「そうであるならば」と、
与えられた状況を受け入れることが下手になったともいえる。
出会いも別れも、それは「運命(縁起)」ではなく、
自分が主体的に選ぶものだ。
(だから、何かの時のためにも、LINEでつながっておいた方がいいのだ)と。
そう皆が思うようになったのは、
私たちが情報に重きを置き、意識に信用を置いているからだろう。
人との出会いでも、旅先での出会いでも、食べ物との出会いでも、
事前に情報を集めることが当たり前のようになっている今の生活では、
縁や偶然に頼ることは、怠惰だとみなされる。
何も知らないのに飛び込むことはなく、
ウェブ上に転がる情報を確認してからなにごとも決める。
今の若い人にとっては、出会いも別れも、
「はじめまして」も「さようなら」も、
なにかに感謝すべきことではないのかもしれない。
そこに「左様なら」を差配する「なにか」や
「グッド・バイ」と人の傍らに佇む「神」はいないのかもしれない。
「一期一会」の出典元である「山上宗二記」には、
「一期に一会の会のように、亭主を敬い畏まるべし」と記されている。
有名な四字熟語である「一期一会」は、もともと、
「亭主を敬い畏まるべし」という、客側の心得に関する言葉なのだ。
茶会において亭主のもてなしを受ける客は、
亭主が繰り出すもてなしを「受け入れる」しかない。
「受け身」の立場にいる客は、積極的になにかを選択したりはしない。
酒が出れば酒を頂き、薄茶がでれば薄茶を頂く。
与えられたものを受容する「客」の心構えとして
「一期一会」はこの世に生まれた。
人や道具との出会いを「選び取る」のではなく、
「受け入れる」のだと教えるために。
さまざまなSNSツールによって、私たちは「卒業」しても、
「サヨナラ」をしなくてもよくなった。
しかし、時代が変わっても人との出会いが「一回性」であることに変わりはない。
遠く離れた人同士の連絡が容易になり、再会が手軽なものになっても、
一度しかない出会いを再現することはできない。
死が身近ではない現代では、実感することが難しくなっているが、
どんなに人がつながっていても、出会いや別れは一度きり。
「次はない」のだ。
新型コロナウイルスにまきこまれた卒業生は、
ドタバタしながら開かれた卒業式でもらった卒業証書と
大学入試の結果を手に、最後のあいさつにきていた。
春からの新しい生活を弾んだ声で話す子たちは、
別れ際、「また会いましょう」と、
僕の連絡先を持ったまま部屋を出ていったが、
もう、この関係性で出会うことは、二度と訪れない。
今後、再会することがあったとしても、もうそれは違う出会いなのです。
だから、私たちは春であることを感じて。
「ああ、もう、そんな時節ですか。左様ですか、左様ですか。左様ならば」
と、別れなければいけません。
「一期一会」の国の住人として、「左様ならば、さようなら」と。