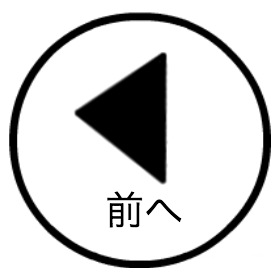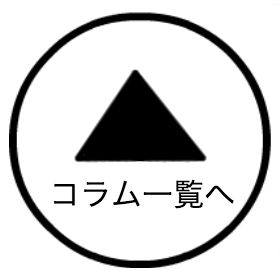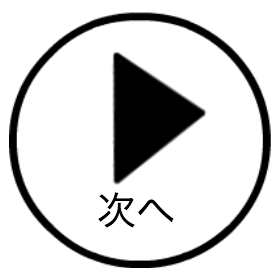ある僧侶が誕生日を祝われていた
「おめでとうございます」
あまりの多くの人たちが誕生日を祝福するからか、僧侶も、「どうもありがとう」と返していたが、音だけが聞こえていたので、その僧侶がどういう顔をしていたかはわからない。
複雑な表情をしていてればいいな、と願う。
誕生日をお祝いするというのは、個人主義時代を象徴するイベントの一つである。
以前は、全員の「誕生日」が1月1日であり、誰もが一斉に、元旦に一つ歳を取っていた。
一人ひとり、別々の誕生日を祝う現代のイベントは、長い日本の歴史から見れば、特殊である。
私はこれまで、ことあるごとに、「男に誕生日はいらない」と訴えてきたが、それも、パターナリズムにつながるらしく、最近は、言うのを控えている。
つまり、「なぜ、男にはいらないのに、女には誕生日がいるのか」と反論されることになるからである。
ただ、女に誕生日が必要で、男に誕生日がいらないわけは、男が嬉しそうな顔をするのが下手だからである。
祝われるにも、資質がいるのだ。
祝われる人は、嬉しそうな顔をする必要があるが、男は、祝ってあげても、ほとんどが期待以上の嬉そうな表情を見せない。
祝いがいのない者には、誕生日などという、「祝われ主」になる機会は与えなくてもいい。
また、誕生日を喜ぶのは、子どもたちである。
一歳一歳、歳を重ねることはおおごとである子どもにとって、誕生日は祝うに値するイベントである。
それに比べると、大人の誕生日は意味が薄く、一歳歳を取ることが、辛ラーメンにかける唐辛子一振りくらいの意味しかない。
特別な日にするほど、誕生日は大したことではない。
大人というだけでも、誕生日の価値はそれほど低いのだから、僧侶にとって、個人的な誕生日なんてないに等しいはずである。
出家とは俗から抜けることではなかったか。
個人としての「私」が生まれた月日などは、ただの数字でしかないはずである。
俗人はなにもわかっていないので、「おめでとうございます」と、自分たちの延長線上で言うかもしれないが、我を捨て、霊性に目覚めた僧侶は、「なにもおめでたいことはありません」と、凡夫の戯言をはねのけてほしいものである。
新年が明けたばかりの元旦に、ドクロを杖に刺して街を歩き、皆のおめでたムードに水を指していた、一休さんの空気の読めなさを見習ってほしい。
宗教人の役割とは、そういうところにある。