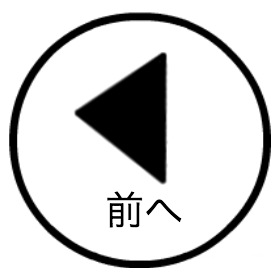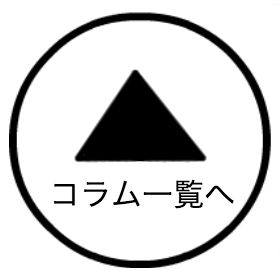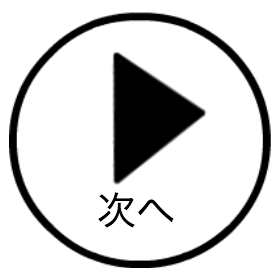漫才の大会であるMー1の今年の優勝コンビの漫才スタイルは、毒舌漫才だった。
社会に毒を吐くスタイルは、これまで脈々と受け継がれてきた笑いの系譜の一つというか、そもそも芸人という立場の人たちが社会の中で担ってきた役割が上の立場の人に毒を吐くということなので、まっとうなお笑い芸人の役割がようやく戻ってきた感もある。
2019年にぺこぱが躍進し、「人を傷つけない笑い」という表現が広まったのは、コンプライアンスが厳しくなった時代に合致してきた結果だった。
その際にも、お笑いが果たして「人を傷つけない」などということが可能なのかという論争があったが、今回も同様に、「人を傷つけにかかる笑い」がはたしてMー1チャンピオンにふかわしいのかという議論が一部で起こっていた。
「人を傷つけない笑い」が幅をきかせ始めていた数年前に、お笑いは根本的に人を傷つけるものと吠えていたのが、爆笑問題の太田光で、その後輩にあたるウエストランドが「人を傷つけにかかる笑い」でM1を制したことは、なんだか批評的笑いの系譜の継承を見たようで、感じ入るものがあった。
現在、お笑い芸人は社会的地位が上がってしまい、文化人のような顔で社会に物申したり、一般人代表みたいな顔でニュースにコメントしたりするようになったが、本来は、芸人は世間の端っこにいるような人たちで、世のお母さんたちに、「そんなん言うとったら、芸人みたいになるよ」と、社会的に駄目な人の模範例として使われるような存在だったはずである。
芸人が本来いるはずの立ち位置から一歩上がり、「人を傷つけない」笑いなどと褒めそやされるようになったことで、人を傷つけるような言葉が吐けなくなった芸人が一番、今回の結果を喜んでいたように思う。
時代が「人を傷つけないもの」や「人に優しいもの」を求めるのは仕方のないことで、それには相応の理由があるのだろうが、お笑いが芸術の一分野である以上、人を傷つけるのはしょうがない。
アートも学問も、美も善も真実も、人々に「ほんとう」を突きつけるような切っ先の鋭いものは、触れるもの皆を傷つけてしまう。
そして、そうした「ほんとう」のものから傷つけられた人が不快な感情や悲しさだけで終わらないようにするのが、「芸」である。
ただの嫌味や悪口で人を傷つけるのは、単なる不快な嫌味であり、負の感情の垂れ流しである。
そうではなく、人の悪口を笑いに変える芸を持つものだけが、芸術としての、文化としての、お笑いである。
社会風刺や毒舌がこれまで生き延びてきたのは、悪口によって人々にカタルシスを与えられるだけの腕と才覚が、芸人にあったからである。
今回M−1を制覇したウエストランドも、これまではずっと僻み・嫉みを一方的に吐き出しているだけの漫才と思われてきた。
それがここ数年で見方が変わり、今回、王座奪還まで至ったのは、彼らの腕が上がったからである。
最近の潮流であった「人を傷つけない笑い」にだって、面白いものと面白くないものがあるように、毒舌漫才にも笑えるものと笑えないものがある。
それを隔てるものは芸人の腕であり、腕が良ければお笑いの中身が、人を朗らかにするものでも、人を刺すようなものでもどちらでもかまわないのだ。
人に対する観察眼からお笑いが生まれる以上、そこは調整次第であろう。
来年以降、どういうお笑いの潮流が流行るのかは予想がつかないが、どんな流れであっても、大事なのは「現実」を笑いに変える腕であり、当たり障りのないおべんちゃらや悪意に満ちた感情の垂れ流しではない。
人々が見たいのは、誰にもできるわけではない「しゃべくり芸」である。
誰でもが簡単に言葉を発信できる時代にこそ、来年は、より言葉が「芸」で包まれますように。
皆さん、よい、お年を。