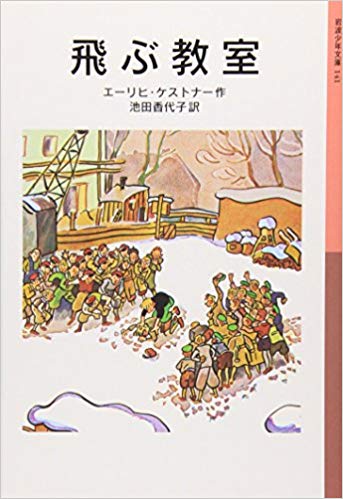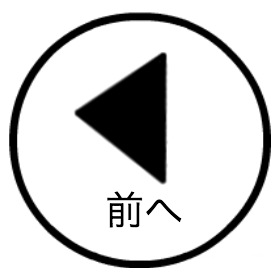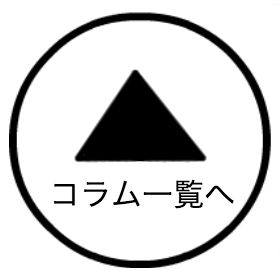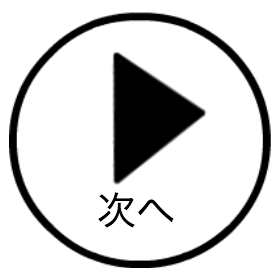みんなが勇気を讃えていた時代の物語
『飛ぶ教室』は、そうした現代と違い、「勇気」や「義」などの徳が、頑然と存在していた時代の物語である。
勇気というものの価値を皆が認め、それを真っ直ぐに主張できた時代であり、徳を子どもに教え、自分自身もその徳を体現しているような先生がいた時代。子どもが素直に、先生を尊敬できていた時代でもある。
そういう時代の物語は、今から読み直すと、登場人物のまっすぐさと力強さが羨ましくもあり、同時に、今の子どもには届かないだろうなと感じるところもある。
「飛ぶ教室」の中で、子どもたちに徳を示すのは、生徒たちの尊敬を集める「正義さん」と呼ばれる舎監長で(なんてまっすぐなあだ名!)、「正義さん」は厳しくも温かい視線で、子どもたちを導いていく。
ある日、普段から、その臆病さをバカにされていた背の小さな生徒が、自分の勇気を示すために、はしごの上から飛び降りて骨折するという事件が起き、病院にかけつけた正義さんは、生徒に対して諭す。
「あのくらいの骨折なら、ちびさん(※飛び降りた生徒)が一生の間、他の者から一人前だと思われないという不安も持ち続けているより、いいんだということを忘れるな」と。
勇気がないと思われるよりは、骨を折るほうがまし。
そんなこと、今の教育現場で、大人が言うことができるだろうか。少なくとも、教室の教壇や体育館の壇上からは言えないだろう。今は、理念や尊厳よりも命や安全が優先されるし、もし、そう思わない大人がいても、表立って、子どもに安全よりも大切なことがあると言うことはできない。
自尊心に比べれば、骨を折るくらい大したことではないと、徳(価値あるもの)の大事さを子どもに語るのは、子どもとプライベートな関係を築いている大人の方が語れるし、少なくとも、教壇の上から、そういった本音は言うことは難しい。
その役目は、時に、叔父さんだったり、先輩だったり、近所の店主だったり、習い事の先生だったりするが、作品の中では、「正義さん」と、近くの廃車に住んでいる「禁煙さん」が担当している。「禁煙さん」は半分、世捨て人みたいな人で、どちらも、社会の建前を知りつつ、大人としての本音を子どもに教えることができる立場の大人たちである。
「飛ぶ教室」の発行は1933年の戦時中であり、作中には、すでに過去のものとなった社会の徳や価値観が読み取れる(その舞台が日本ではなく、ドイツであったとしても)。
物語を読み、過ぎ去った時代の空気を感じることは、今の時代の常識を客観的に見ることにもつながる。そういう意味で、これはもう、子どもではなく、大人が読み返す本なのだろう。
子どもは、「正義」を正面から説く物語を読んでも、もうピンとこないだろう、
教育とは、多くが、言葉を通じてなされていく。以前言葉で子どもに伝わっていたものが伝わらなくなっていることを、私たちは、過去の本を参考に、たまには考えるべきだろう。
言葉の衰退を、むやみに見過ごしてはいけない。