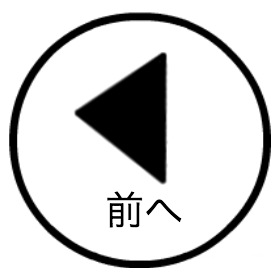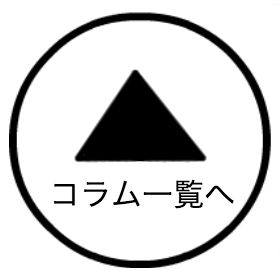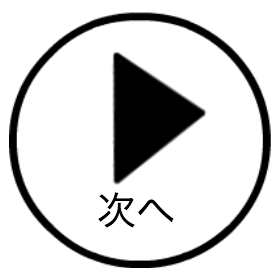日本人は努力が好きである。
なんだって努力でなんとかなると思っている節がある。
思えば、中学時代の校長が講話の中で好んで引用していた言葉に「為せば成る」というのがあったが、この言葉は結構な「努力信仰」の言葉である。
為せば成る 為さねば成らぬ何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり
米沢藩主・上杉鷹山が言ったとされる言葉だが、要約すると、「やりゃできる」ということである。
教師たちが好きそうな言葉だなと、今になって思う。
「努力が大事」だと日本人が考えるの裏には、「能力は頑張れば獲得できるもの」という考えがある。
さらにいうと、後天的な努力によって能力が得られるという考えの裏には、能力は初期状態には備わっていないという考えがある。
「誰もが最初は一年生」であり、最初から能力があるわけではない。
「初期設定時には能力は付けられていないので、自分で後付けしてください」
というわけである。
そうした考えは当然だと考えるかもしれないが、世界には、「能力は最初から備わっている」と考える人達もいる。
アメリカ人である。
彼らは、能力はすでに装備されており、大切なのは、「その能力に気づくこと」であると考える。
「己の努力によって能力を獲得していく」というよりは、「自分にすでに備わっている能力を努力によって取り出す」くらいの感覚に近いのかもしれない。
だから、そこで大事になるのは、「努力」の前に、「自信」である。
「自分はすでに能力を手にしているのだ」という自信。
「自分には信じられない能力が潜んでいるのだ」という自信。
日本人は、「まだ持たざる己」という、低い場所にいる自分を認識することから、高みを目指す道が始まると考えているが、アメリカ人は、「既に手にしている私」という、高みにいる自分を想定することから、そこに辿り着くまでの道のりが始まると考える。
アメリカ人の成功者たちを見ると、皆、一様に、自信満々な姿に見えるが、それは成功したから自信に溢れているのではなく、彼らは、成功する前から自信に満ちあふれていたのである。
最初からその自信がなければ、アメリカで成功することはない。
そうしたアメリカ人の「自信の重要性」が如実に表れているのが、アメリカ人が愛する童話『オズの魔法使い』である。
フランク・ボームが著した「オズの魔法使い』は1900年に第一作が著されて以来、多くの熱狂的読者を獲得し、計14作に登る出版シリーズだけでなく、多くのミュージカル化、映画化、ゲーム化がこれまで繰り返されてきた。
最近も、2019年にNETFLIXでリメイク版がリリースされるなど、いまだに人気を博している。
『オズの魔法使い』は、アメリカ人の作者によってアメリカを背景に書かれた最初の本格的ファンタジーであるが、作中には絶大な力を持つ者も並外れた力を発揮する者も登場しない。
主人公のドロシーは、魔法使いのいるエメラルド・シティへと旅をする途上で仲間に出会うが、彼らはそれぞれ欠点を抱えており、カカシは「脳」、木こりは「心」、ライオンは「勇気」を欲していた。
彼らは魔法使いであるオズにそれらをもらえるよう望むが、最終的に、オズにそれらを与えられるような力はなく、すでに彼らは自身が欲するものを手にしているのだという結末に至る。
カカシ、木こり、ライオンの三者は、すでに必要なものを有しており、彼らに不足していたのは、自分への信頼、つまり、自分には知恵・勇気・心があるというという「自信」だけだったのである。
「足りないのは自信であり、自信さえあれば、物事はうまく運ぶ」
そうした教訓を持つこの物語は、非常にアメリカ的である。
アメリカ人ジャーナリストのマーク・ハーツガードは、「『オズの魔法使い』が今も人々に強い感動を与えるのは、自分たちも、主人公のドロシーが歌っていたように、思いきって見た夢が本当に実現するような国に暮らしているのだという確信が深まるからだ」と言う。
ただ、アメリカ人がここまで「本当は能力があるんだ」と信じこむ姿は異様でもある。
日本人からすれば、「能力」がないなら後からつければいいし、なんなら、能力がないならないで仕方ないとも考えるが、アメリカ人はそれに恐怖にも似た感情を抱く。
いや、私には、能力が備わっているのだ。
私は「有資格者なのだ」と。
そこにはやはり、キリスト教の思考が影響しており、「選ばれし者」というニュアンスが香る。
マックス・ウェーバーが『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』で看破したように、プロテスタンティズムが持つ勤勉性は、本来はプロテスタンティズムとはまったく関係ないはずの資本主義を推し進めることにつながった。
アメリカの祖であるピューリタンたちは、「救われるか救われないか」は神の予定によるものだとし、それが人間には理解できない以上、「自分は救われるはずだ」と信じて勤労に励むしかないと考え、勤労に励んだ。
人は「神に選ばれているかもしれないし、選ばれていないかもしれない。選ばれていれば、天国に行けるし、選ばれていなければ、努力しても天国には行けない」と言われると、努力して真面目に生きるようになるのだ。
最初から選ばれているかどうか決まっていて、この世での努力が意味をなさないなら、だらだらと不真面目に生きていてもよさそうなのに、人は、必死に、神のお眼鏡に叶うような生き方をしたがる。
「努力した者が選ばれる」でないことはわかっていても、「選ばれている人間である私だからこそ、こんなにも真面目なのです」とアピールするのだ。
すでに選別は終わっていたとしても、自分で自分を納得させるためのアピール。
現代のアメリカ人が自分の中に能力があると信じるのも、それと同じ論理であろう。
自分の内部に能力が備わっているのかいないのかわからないとしても、自分の中に潜む能力を信じて突き進むしかない。
「能力」が先天的なものであるならば、それにかけて信じるしかないのだ。
『オズの魔法使い』の中で、カカシ、木こり、ライオンの三者は、最終的にそれぞれ、エメラルド・シティ、西の国、大きな森を治める支配者になる。
つまり、彼らは「自信」さえ手にいれれば、支配者になれるような大人物たちだったのだ。
こうした、日本人にとっては予定調和にも思えるような結末も、「選ばれし者は最初から決定されている(そして”あなたは”選ばれている)」以上、”あなた”がなすべきことは、自分の能力を疑わず、自信を持って職務に励むだけであるという教訓を信じるアメリカ人たちにとっては、琴線に触れるものなのだ。
このような考え方は、アメリカ的とも言えるし、カルヴァン的ともいえる。
そして、そうした、アメリカ人のマインドとアメリカ建国の基礎に紐づく「自信」という性質を確認させてくれる物語を、アメリカ人は何度も何度も繰り返して読むことによって、定期的に確認し、国民としての一体感を強めているのだろう。