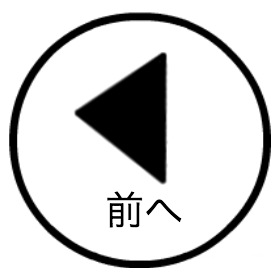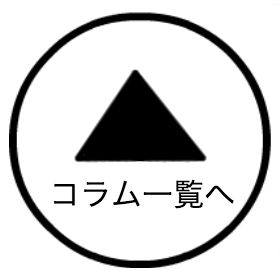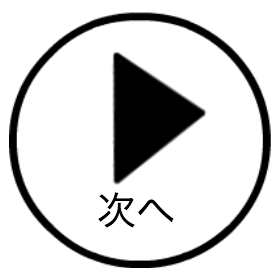小学生の頃、スケッチ大会というのイベントがあった。
首から画板をぶら下げて、外に出かけ、好きな場所で好きな絵を描く。
どこで描いてもいいという自由度の高いイベントだったのだが、毎年、描いていたのは同じ場所だった記憶がある。
どこで描いてもいいと言われても、絵を描くことに自信のない子どもたちは、人工物や動物など、カタチのはっきりしたところに向かう。
絵の上手い子たちのように、樹や花のような植物には手を出さないし、空や雲のような風景にも手を出さない。
しかし、いざ牛小屋に行き、牛を見ながら牛を描こうとしても、牛は牛で難しい。
牛を描いているのに、どうやっても頭と胴体のバランスが取れず、牛に見えないし、4本の脚が直線に並んでしまい、立体的に見えない。
下手くそは、いくら対象を限定しても、下手さが前にでてしまう。
年に一度のスケッチ大会は毎年開催されていたが、回を重ねているからといって、上達することはなかった。
下級生のときは下級生なりの下手さで、上級生の時は上級生なりの下手さだった。
そう思い返すと、学校の先生というのはひどいなと思う。
下手な子どもを下手なまま放置して、毎年、同じ惨めさが繰り返される。
歳を追うごとに絵を描くことが嫌になっていった。
小学5年生の秋のスケッチ大会。
例年通り、牛小屋をモチーフに作品を仕上げていた僕は、絵ができあがるにつれて、自分の絵の下手さにうんざりしていた。
鉛筆で描くだけならまだいいが、絵の具で色をつけていくと、さらに自分の絵の稚拙さが目立ってくる。
絵がうまく描けなくても、絵がうまいか下手かくらいはわかる。
絵の見方がどんなに自由だとしても、これは、どうみても下手。
あぁ、早く終わらせて、遊びに行きたい。
そう思いながら牛小屋に茶色の絵の具を塗っていると、背後から、ぼくの絵を覗き込んでいる友達がいた。
その子は、スケッチ大会や夏休みの課題など、絵に関する課題でいつもなんらかの賞をもらうような、絵の得意な子。
絵が得意なくせに真面目に描かないので、自分の絵をさっさと終わらせ、ぶらぶらしていたのだろう。
ぼくの絵をじっと覗き込んでいる。
ドギマギ。
その子の視線に耐えられなくなったぼくは、半ば自虐的に、「もう、この絵、どうしていいかわかんないよ」とこぼした。
すると、その子は「貸して」と、僕の筆を取り、パレットに群青色と少しレモンを出し、茶色で塗りつぶされた牛小屋の壁に色を足し始めた。
ぐ、群青とレ、レモン?
僕はポカンとした。
牛小屋の壁は茶色には見えても、群青やレモン色ではなかった。
この子、色盲じゃないよな・・?
だからといって、絵の上手い子に意見するような図々しさはなく、黙ってその子の描く様子を見ていると、茶色一辺倒で塗られた壁に、トントントンっと、軽く筆が置かれ、壁の表情が変わっていく。
のっぺりと平面的だった絵に立体感が生まれ、絵に厚みが増してきた。
す、すごい・・・というか、う、うまい。
その子は、結局、牛小屋の壁の一部だけを立体的にした後、すぐに、別の友だちのもとへ行ってしまった。
親に手伝ってもらった読書感想文みたいに、ぼくの絵は、一部だけが明らかに別人の手によるものとわかる仕上がりになった。
その子が去った後、その子のやり方を真似して描いてみたが、まったく、同じような立体感が出ることはなかった。
ただ、絵が上手いってことがなんだかわかったようで、自分が下手な理由に納得がいったようで、なんだかいい気分だった。
その子にあって、ぼくにないものは絵の技術と知識だった。
もちろんそこには、美的なものに対するセンスの違いがあるのだが、明らかに、その子と自分とでは、絵を描くことに対してできることが違っていた。
絵は好きなように書いていいんだという、まやかしの「自由」(という名の「放置」)の中で、ぼくはなんの絵画的な技術も持ち合わせていなかったために、六年間(というかその後も)、美術が嫌いなままだった。
下手なのに、うまくなるための技術や、多角的に見るための知識を得る機会がなかった。
これまで図工や美術の時間に、茶色に見えるものに群青やレモンを塗っていいなんて教えてもらわなかったし、絵の具の塗り方によって立体感が変わるなんてのも、聞いてなかった。
でも、たぶん、その子は、それを誰かに教わることなく知っていたのだ。
それがセンスだし、好きということだ。
好きな子は放っておいてもいろんな発見をする。
しかし、好きでない子は放っておいたら、なんの発見もしないし、なんの上達もしない。
だから、自由な表現をさせる前に、教えるべきは、技術と知識なのだ。
できることが増えれば、そこに表現力や創造性が発揮される余地はある。
蓄積のないところに自由は生まれない。
それは、スケッチ大会だけでなく、自由研究でも読書感想文でも創作ダンスでも同じである。
自由は大人にも子どもにも難しい。