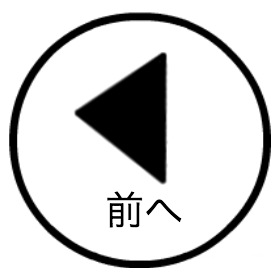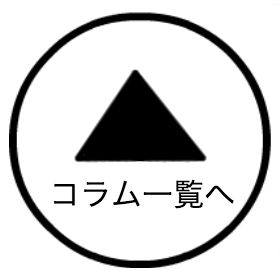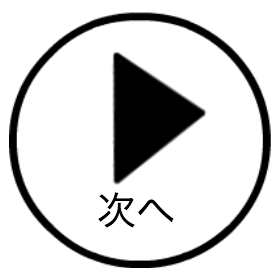「人を見る目がある」という言い方をする。
「人を見る目がある」というのは、まだ現れていないその人の良さを見抜けるということなので、数学オリンピックで優勝するような学生に、「君は数学の才能があるよ」と言っても、それは、「人を見る目」があるとは言わない。
まだ油絵を書いたことがない子に対して「君、油絵を書いてみたら」と薦めたり、外野手をやっている子に対して「君、ピッチャーに転向しなよ」と言ったり、まだ顕在していない何かを見なくては「人を見る目がある」ことにはならない。
「人を見る目があるとかない」という言い方が一般的にあるということは、「人を見ること」は難しいという前提が社会にはあるのだろう。
人は人を正しく見れないのだ。
多くの場合、人は、「その人が見たいように他人を見る」し、さらにいえば、「自分を見るように相手を見る」。
だから、例えば、自分と同じような道をたどっている後進についは、適切なアドバイスができるが、自分とまったく違う道をたどっている後輩に対しては、何もアドバイスができない。
しかし、人は、適切な判断やアドバイスができないと思われたくないので、相手を見る目が備わっていない場合でも、アドバイスや指導をしてしまう。
そして、たいていの場合、それは不適切な結果を生む。
「人を見る目」が肝心になってくるのは人事に関してである。
特に、企業のトップの交代というのは難問である。
近頃は、大企業のトップ選びは、役員や株主が決定するが、過去の日本の大企業や、現在の上場企業以外の会社では、次のトップを「現職のトップ」が任命する。
そして、その禅譲がうまく行かず、業績が下がったり、安泰だった株価が一気に下がったりすることは特に珍しいことでもない。
それまで企業の舵取りをうまくやってきたトップが、これからの会社に必要なリーダーシップに関しては誤って判断してしまうのは、どういうことなのだろうか。
よくなされる分析としては、「トップが自分に似た部下を選ぶから」だというものである。
会社に必要なリーダーを冷徹に判断したのではなく、情やお気に入りで次期トップを選んでしまったのだと。
それは、大きく捉えると、自己愛である。
人は自分がかわいいために、自分に似た人を好意的に見てしまう。
しかし、企業は生命体のようなものなので、似たようなトップが続けば新陳代謝が鈍り、新しいものは生まれなくなる。
そもそも似ているということが、リーダーとしての質を保証するわけでもない。
ザリガニが伊勢海老の代わりに主役を張れないのと同じで、良いリーダーに似た人が良いリーダーであるわけではない。
また、企業のトップが自分に似ている人を選ぶのは、なにも自己愛からだけではない。
そうではなく、自分と似ていない人を評価する術を知らないからでもある。
国内の開発畑を歩んできた人は、国際的なキャリアを歩んできた人をどう評価していいのかわからない。
発想力や創造力でのし上がってきた人は、システム作りや組織運営を重視してきた人がどの程度のものなのかわからない。
人を評価するには、評価するだけの見識が必要なのだ。
それは、企業に限らず、教育現場でも同じである。
教師も、子どもを見る際、自分の子供時代を通して見ていることが多い。
自分に似た子どもには同情的になり、かつて自分をいじめていた子どもに似た部分がある子どもには淡白になる。
教師も人なのでそれは当たり前のことなのだが、教師という仕事は、「建前」を大切にするので、そのことを認めない人も多い。
自分はフラットに子ども達を見ている。
その思い込みは、より子どもたちを見る目を曇らせ、不適切な指導につながる。
子どもであれ、大人であれ、一人ひとり違う人間である以上、相手を理解することは難しい。
「親子」でも「夫婦」でも難しいのだから、他人が他人を「わかる」ことは容易にはできないと考えるべきだろう。
そう考えることができれば、「難しい」なりに、手放したり、任せたりすることができる。
なにも教師は一人だけではない。
どこか一人の教師がその子のど真ん中にヒットしてくれればラッキーくらいに考えて、教師が子どもを手放すことも重要である。
民藝の提唱者・柳宗悦は、ものをみるときは「じかに見ろ」と言っていた。
自分の好みや嗜好を廃して、そのものを「曇りなき眼」で見ろと。
それはなかなかに難しい。
ものでも難しいということは、人の場合には、それに輪をかけて難しいと知るべきだろう。
そして、「ものを見る眼」を養うためには、一流のものをたくさん見るしかないという。
それは人でも同じだろうか。
「一流のもの」は想像がつくが、「一流の人」とは誰のことであろうか。
そして、一流のものを見て、養われるのは「美を見る眼」であるだろうが、一流の人を見て養われる眼とは、なんだろうか。
「善を見る眼」だろうか、それとも「人自体」を見る眼というものがあるのだろうか。
例えば、宮大工は、将来宮大工として大成しそうな若者を見る眼は持っているかもしれないが、将来、陸上選手として大成しそうな若者を見る眼は持っていない。
それは、それぞれの分野の話である。
これからどこに向かっていくかわからない小さな子どもを、大人はどういう眼で見たらいいのだろうか。
京都の民藝品を見ていると、そういうことを思う。