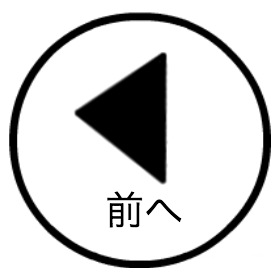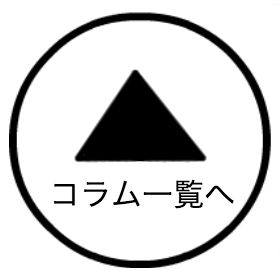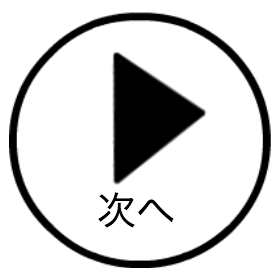『だれも知らない小さな国』佐藤さとる・作
みんな、自分の中の「子ども」を引きずりつつ大人をやっている
佐藤さとるさん作『だれも知らない小さな国』は 、昭和34年に発売されたファンタジーで、その後、『コロボックル物語』としてシリーズ化された。
コロボックルというアイヌ伝承に基づく小人と人間の交流を描いた物語で、およそ60年以上読みつがれている。
五年ほど前に、佐藤さとるさんに代わって有川浩さんが続編を書くという、奇妙な続き方もしている。
この話の物語の主人公は、小さい頃に、コロボックルらしい小人が山の中にいることを肌で感じたものの、実際に目にすることはできず、そのまま大きくなっていく。
大人になり、改めてコロボックルたちに出会った彼は、清らかな小山で慎ましく暮らす彼らと交流を重ねていく。
自分の「内なる世界」であるコロボックルとの関係を大事にする主人公は、世間的には、電気整備士として働いているが、会社の同僚や上司と話す場面は、物語の中には出てこない。
休日になるとすぐにコロボックルのいる小山の小屋に行き、彼らと住みよい小屋の改善に勤しむ彼は、会社の人からどんな目で見られていたのかと想像する。
仕事中に、コロボックルとコソコソ会話をしている主人公の姿は、どうみても、仕事を懸命にやっている人のそれではなかっただろうと思う。
その主人公の姿は、仕事よりも趣味を最優先する最近の若い人たちを想起させる。
仕事より自分の好きなことを優先する若者は、会社での人間関係もドライで、会社の人に自分がどう見られているかを気にしない。
なるべく、自分の趣味に時間を費やし、趣味のために、あえて昇級を望まなかったり、恋人を作らなかったりする。そういう類の若者は、今では特段、珍しくはない。
そういった「自分の趣味に生きる人たち」=「他人に理解されない、自分の中の世界を大事にする人たち」は、以前の社会では、「大人」とはみなされなかった。
大人とは、社会的な仕事を最優先し、責任を背負う人のことで、社会的責任よりも自分の好きなことを優先するのは、未熟者のすることだった。
やりたいことをやれるのは、「子ども」の間だけで、自己がまだ確立されていない子どもだけが、社会的な責任を免れた。
そして、その子どもたちも、大人になっていく段階で、自分の内面世界や好きなことを心の奥に引っ込め、世間の価値に従って生きるようになる。
それが、今や、大人になっても、自分の好きな世界にこもることが許されるようになった。「大人」の定義も、時代によって、どんどん変わっていると考えるべきなのだろう。
ただ、大人が、好きなことをできなかった”以前”より、もっと”以前”にさかのぼってみると、日本には「隠居」というシステムがあり、大人でも好きなことができる仕組みがあった。
江戸時代は、基本単位としての”家”があり、その戸主は社会的責任を負った。
しかし、家督を下の世代に譲り、隠居すれば、社会的責任から降りることができた。
「隠居」と聞くと年を取ったおじいさんをイメージするかもしれないが、当時、体力的な余力を残しながら、早めに隠居した人も少なくなく、彼らは、世間的な責任から逃れ、自分の趣味である、文芸や学問、唄や踊りなどに没頭した。
彼らは、一個人として、自分の好きなことをして暮らし、中には、日本の文化史に残る偉業を残した人もいる。
江戸時代は、大人としての責任を果たすべき人と、果たさなくてもよい人の間に、はっきりとした線が引かれていた。
現代は、その点が曖昧で、多くの人が、自分の中の「子ども」を引きずりつつ大人をやっている。
また、寿命が伸びるに従って、高齢でも働き続ける人が増えたことで、多くの高齢者が「大人」を引きずりながら「老人」をやっている。
社会的責任を負う「大人」と、それを負わなくていいはずの「子ども」や「老人」の曖昧な境界が曖昧になっていることは、社会的な責任の所在が曖昧になっていること。
そして同時に、一人ひとりが、社会的立場の変化によって、自分がやるべきことや自分の役割などによって、自己を規定することができなくなっているということでもある。