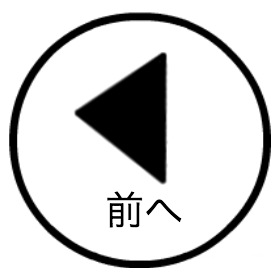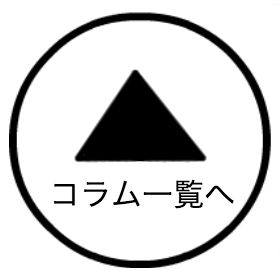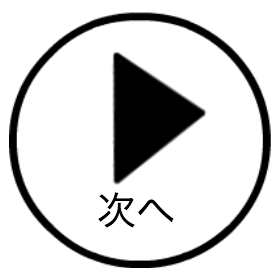『だれも知らない小さな国』佐藤さとる・作
良質なファンタジーは、読者を異世界に連れていき、パッと現実世界に帰す
コロボックルと交流を重ねる主人公は、その小人の存在を、会社の同僚を含め、周りの誰にも言わずに黙っている。
言ってもバカにされるか、頭がおかしいと思われるだけだからだが、彼にとって、コロボックルは自分の「内なる世界の住人」であり、外側の人たちに理解されないとしても、一向にかまわないのだ。
彼は、終盤、コロボックルたちが住む小山に、高速道路が通される計画があることを知り、どうにかその計画を変えようと奮闘する。
その計画が実行されれば、彼の「内なる世界」は破壊されてしまう。
初めて訪れる「内なる世界」と「現実社会」との衝突。
主人公は当初、簡単に、人間たちが決めた計画に従おうとするが、ある女性と関係が深まっていく中で、翻意し、人間が進める計画に反対しようと決意する。
それは、周りの決定に従うこと(=自分の「内面世界」を捨てること)が、大人になることだと、半ば諦めていた主人公が、すんでのところで、自分の中の「子ども」を引きずりながらでも大人になれると思った瞬間でもあった。
この本が刊行された昭和34年には、主人公に同調する大人は少なかっただろう(だからこそ、本著は、児童文学に収まっていた)。
しかし、大人と子どものラインが曖昧な平成・令和の時代には、自分の「内なる世界」と「現実社会」を両立させたいと考える大人はたくさんいる。
今は、好きなことだけをして生きていけるわけではないが、好きなことをしながらも生きていける時代でもある。
自分の中の「子ども」と、外に向ける「大人(の顔)」を、どうバランスしていくかが、多くの人にとって課題なのだ。
この物語は戦後に描かれたファンタジーで、他のファンタジー作品同様、現実世界には存在しない類のキャラクターが登場し、現実に起こりえない超常現象が巻き起こる(程度は軽いが)。
読者はそれらの異世界の描写を読むことで、登場人物たちとともに非日常の世界を生き、特別な体験をする。
ファンタジーは、そうやって、読者を異世界に連れ去るが、良質なファンタジーほど、異世界に引きずりこんだ読者を、現実世界に、パッと帰す。
ファンタジーに限らず、民話や伝説の基本構造の一つは「主人公が行って帰ってくる物語」で、スタート地点を離れた主人公が異世界に飛び込み、様々な経験を積んだ後、始めの場所に戻ってくることで、物語は完結する。
読者は、現実世界では体験できないことを追体験することで、擬似的に、人生を生き直したり、再生したりする。
しかし、生身の人間である私たちは、異世界(本)の中で生きることはできない。
私たちは、どうしても現実世界で生きねばならず、異世界から帰ってくる必要がある。
名著として長年愛読されているファンタジーは、読者をいつまでも異世界にとどまらせておかず、ぐいっと異世界に連れ込んだと思うと、パッと、現実世界に帰す。
作品の主人公が「異世界に行って帰ってくる」のと同じように、読者をパッと異世界に連れていき、現実世界にパッと帰す。
そうやって、「現実世界」で生きる私たちに、ある種の力をファンタジーは与えるのだ。
『だれも知らない小さな国』で、コロボックルと一緒に、彼らの住処を守った主人公は、その過程である女性と出会い、初めて、コロボックルの秘密を打ち明ける。
二人は秘密を共有することで、関係を近づけていき、物語内では結ばれることはないが、今後、二人が結ばれるだろうことを、読者は予感する。
その女性は、主人公にとって「内なる世界」の理解者であり、「現実社会」との架け橋だ(女性にとっての彼も、またそうだ)。
そして、主人公とその女性を近づけたのも、コロボックルたちだった。
良質なファンタジーが、読者を異世界にパッと連れていき、パッと戻すように、主人公を小人の世界に連れ込んだコロボックルたちも、主人公をいずれ「現実世界」に戻さなくてはならないと、知っていたのだろう。
人間は小人と仲良くすることはできても、小人の世界で生きることはできない。
「内なる世界」を共有できる女性と出会うことで、主人公は、「現実社会」に、じょじょに帰っていく。
そうやって、自分の中の「大人」と「子ども」のバランスを取るのだ。
物語は、どこかへ「行った者」が帰ってきて、はじめて終えることができる。
終われば、また次に行ける。
それは物語の主人公も、物語の読者も同じ。
始まりと終わりを繰り返して、人は成長していく。