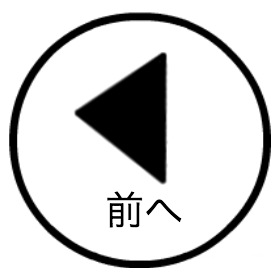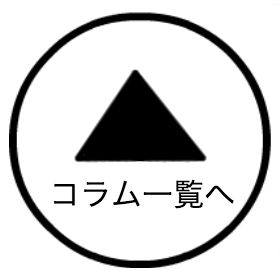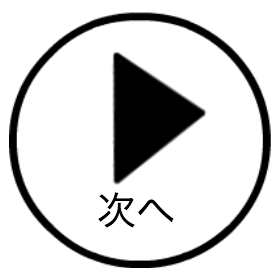この世で「風船と子ども」ほど似合うものはない。
風船は子どものためにあり、風船は子ども以外が持って様になることはない。
子どもに風船が似合うのは、子どもが風船を何個か持ったら、空高く飛んでいってしまいそうだからかもしれない。
童話やファンタジー作品の中でも、風船によって飛んでいく子どもというモチーフはあるが、子どもはファンタジー的で詩的な存在なので、実際は風船によって空に飛んでいくなんてことはなくても、飛んでいったかのような気になってしまう。
詩的な存在は、空想と現実の境界がない。
「お話」の世界とともに、この世界を生きている。
「お話」の中で生きる子どもたちは、秋になってどんぐりや木の実が落ち始めた山を歩いている時にも、昨晩聞いたファンタジーの話を一人で繰り返しながら、どんぐりを拾っている。
アボカドを「恐竜の卵」だと信じて疑わない年齢の子には、どんぐりや木の実さえも、なにかの「お話」につながる可能性で溢れている。
そんなことを思いながら、娘と山の中を歩いていると、手にあまるくらい大きな松ぼっくりを娘が拾ってきた。
「ねぇ、この中、なに入ってるの?」と松ぼっくりを振りながら聞いてきたので、
「中には何も入ってないんじゃないの?音もしないし」と、
そもそも松ぼっくりに「中」とか「外」とかないしなぁと思いながら答えると、
「入ってるよ。ほら。中に”秋”が入ってるじゃーん」
と当たり前のような顔をした。
子どもというのは、「空想」と「現実」の間の境界線がないのと同時に、
「抽象」と「具体」の間の境界線もないんだなと感じる。
彼女らにとって、時に、「秋」は掴めるものであり、
「松ぼっくり」は「中」と「外」があるものなのだ。
「現実」とは多重奏なのですね。