
もう一つビッグイシューからの話。
今回の特集は「YA文学」というものだった。
初めて目にする言葉だが、「ヤングアダルト文学」の略だという。
中学生・高校生向けに書かれたような、
児童文学と普通の文学の間に位置するものかなと思ったが、
記事の定義では「大人が背負わなければならない社会的な
問題を背負わされた子どもを描いた文学」ということらしい。
「クリスマス・キャロル」とか「赤毛のアン」とか
「飛ぶ教室」とか・・・。
こういう風に分類することの是非はよくわからないが、
このジャンルの作品は好き嫌いがわかれる。
なにせ、主人公が小学生や中高生だ。
子どもを描くのはけっこう難しい。
大人びていても「そんな小学生いないよ」と思うし、
あどけなさすぎても「今の中学生はそんなウブじゃないよ」
と思う。
本当はというか、現実には様々な子どもがいて、
大人が知らないような難しい言葉を使う小学生もいるし、
微積分習ってても家で寝ションベンしてしまう高校生もいる。
現実には色々な子どもがいるが、
それが物語の中に出てくると違和感しか感じない。
物語だけに、ある程度のリアリティを読者は求めてしまう。
リアリティがないのに、違和感を感じさせないとしたら、
それは作者の筆力がすごいからだろう。
「海辺のカフカ」の15歳の主人公なんて、
日本中探しても絶対どこにもいない。
その前に、「海辺のカフカ」はYA文学ではないだろう。
あれ、じゃあ「桐島、部活やめるってよ」はYA文学だろうか。
「桐島」は大人が背負わなければいけない社会問題を背負ってる
だろうか。
「三四郎」は、「坊っちゃん」はYA文学だろうか。
夏目漱石は日本の近代を背負っていたが、どうだろうか。
なかなか、分類とは難しい。
大人が児童文学も読むように、
子どもも読みたい本を読めばいいと思う。

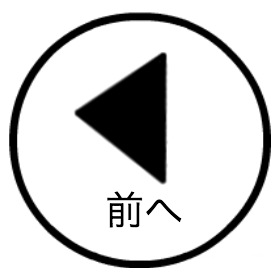
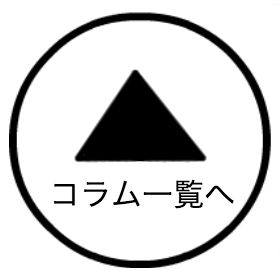
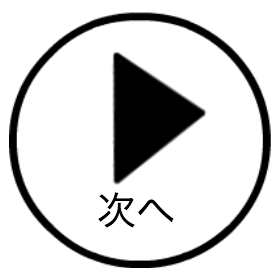
コメント