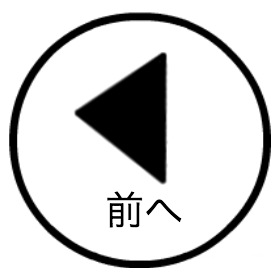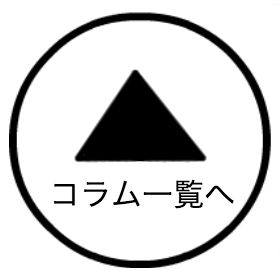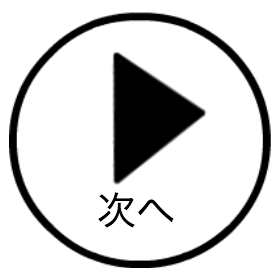寿司屋のカウンターに座っている(つまりは「カウンターのある寿司屋にいる」ってこと)。
人に奢ってもらう時くらいは、回らない寿司屋に来るに限る(素封家)。
カウンターには、僕らの他に、キャバクラの「同伴」らしく、若い女性と中年の男性客がいる。
(寿司通は「カウンター」ではなく「付け場」と呼ぶらしい)。
男性客は、女性にいいところを見せたいのか、饒舌に大将に話しかけるが、大将は愛想がなく、あまり会話のキャッチボールは弾んでいない(キャッチボールというか「壁当て」だ)。
それでもめげない男性客は、女性にネタの好みを聞き、「大将、ヒラメの昆布〆、頂戴!」と、片手を挙げて注文する(ダサっ)。
無口な大将は、手元の包丁の動きを止めずに、注文を小声でつぶやくように復唱する。
「こぶじめ、一丁」
こぶじめ・・・。
そういえば寿司屋は、「昆布〆」を「コブジメ」と呼ぶ(かっこいい)。
「コンブ」の真ん中の「ン」を抜かして「コブ」と呼ぶのは、なんだか異例に聞こえる。
我々が使っている日本語では、言葉の「前」を取るか「後ろ」を取るのが普通である。
(前:アルバイト→バイト)
(後:ストライキ→スト)
「コンブ→コブ」のように、単一語で、「真ん中」だけを取る例なんてほとんどない。
なぜ「昆布」だけは、「コ」でも「ブ」でもなく、真ん中の「ン」を抜くのか。
この異例の抜き方は、もしかしたら昆布が「さっぱり」していることに由来している可能性がある(これを「ン」抜き仮説と呼ぼう)。
試しに、「昆布」を「コブ」と呼んでほしい。
そうすると、「さっぱり」することに気づくだろう。
「コンブ」から「ン」を抜くと、「さっぱり」する。
つまり、味に近づくのだ。
おそらく、これと同様の例は他のさっぱりした言葉にもあると思い、色々と探してみたところ、これが、ないのだ。
おそらく、その原因は、昆布以外の「ン」有り言葉は、すべて死に絶えたことにあると思われる。
「昆布」は奇跡的に、「コンブ」と「コブ」、両方の言い方が現代まで残ったが、ほとんどの「ン」有り言葉は「ン」があった頃の元型が残されなかった。
つまり、世の中の「さっぱりした言葉」は、昔はどれも「ン」が入ってたが、後世には、「ン」が取れた後の形だけが残されたために、誰も『「ン」有り時代』の言い方を覚えていないのだ。
その昔は、「サバ」も「サンバ」、「キス」も「キンス」で、「サワラ」も「サワンラ」、「カツオ」も「カンツォ」だったのだ(カンツォて!)。
つまり、「コンブ」は古い言葉で、「コブ」の方が新しい言葉なのだ。
歴史の中で、人はさっぱりした「味」に「言葉」を寄せていったというわけだ。
この理論で考えると、おそらく、「梅干し」も昔は「うんめぇ干し」だったはずだが、「梅干し」という音が与える印象と、「うんめぇ干し」が与える印象はあまりに違いすぎた。
そのため、「ン」がだんだんと抜かれるようになったのだ(梅干しは唸るほど「旨ぇく」はない)。
さっぱりしたものから「ン」を抜くと、「本質」に近づく。
だから、我々の日本語は、この500年ほどの間に、さっぱりした言葉のほぼすべてから、「ン」を取り去った。
おそらく、この令和の時代に生きている皆さんは、『「ン」有り時代』のことをまったく知らないゆえに、この「ン仮説」を信じないだろうが、私はここに予言しておく。
200年後の日本の食卓で交わされる会話において、「ポン酢」は「ン」が抜かれて「ポ酢」と呼ばれているだろうと。
そして、「ポ酢」が、かつての日本で「ポン酢」と呼ばれていたのだと教える人を見て、笑うだろう。
「お前、『ポン酢』て!」と。
それはあたかも「カツオ」がかつて「カンツォ」だったと聞いて、「カンツォて!」とツッコむ現代人と同じくらい滑稽な姿なのである。