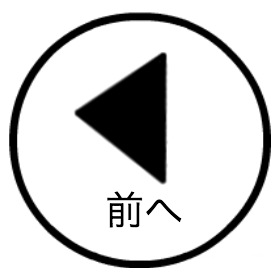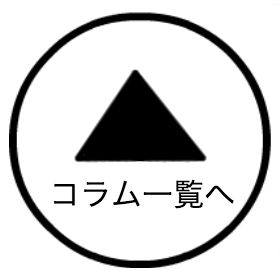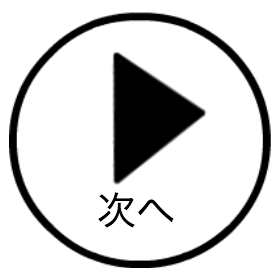中学3年生の頃、自分の中の「議論熱」が高まって、誰かと「議論」がしたくてたまらなかった。
けれど、学校では、誰も「議論」してくれる友人がいなかったので、休み時間も廊下側の席で数学の問題を説きながらふてくされていた。
高校にあがると、誰かと議論したりもするんだろなと静かに「議論熱」を高めていたけど、時代は「スカし全盛期」で、「熱さ」よりも「冷め」こそが「クール」だったため、高校に入学しても、皆、議論どころか、墓穴を掘らないように探り探り会話する日々だった。
結局、現実の世界では誰も語る人がいなかったので、テレビの中で同年代が話し合ってる番組を眺めていた。『真剣十代。しゃべり場』である。
教育テレビ(現Eテレ)の番組である『しゃべり場』は何期か続いたのだが、その1期目の出演者には、学校に行ってない人とか大工の見習いしてるロン毛の人とかが出ていて、若者らしく、「学校なんて行っても意味ないだろ」みたいな話、というか不満と不安のぶつけ合いで盛り上がっていた。
番組には十代の子たちに混じって、一人だけ大人が参加するきまりがあった。
聞き役みたいな立場で、子どもたちが議論している合間にちょろっとだけ話すのだけど、その「大人役」で一回目か二回目に出てきたのが、なんと、”家元”こと、落語家の立川談志だった。
今考えれば、「教育」から最も遠い家元なんかをキャスティングしたの誰だよ、と思うけど、番組が始まって、十代たちがしゃべっているのを最初の方こそ聞いていた談志師匠だったが、結構序盤の方で、聞いてらんなくなって、議論の途中で控室に帰ってしまった。
十代であった一視聴者の僕は、「え、帰るの?この後、どうすんのよ?」と、まずもって立川談志が誰かわかってなかったから、大人のわりに勝手だなぁと思っていたけど、今思えば、談志師匠は帰って正解というか、帰ることが大人の正しい反応だなと思ったりもする。
談志師匠は「帰る」ことで、「お前らの話は聞くに値しない」と言ってるわけだけど、正直、十代の話なんて聞くに値しないのは確かなわけで、現実世界では、それを分かりつつも聞いてあげる大人というのも一方では必要であるが、他方では、聞いてあげない大人、それは、忙しいとか興味ないから聞かないではなくて、「聞いてみたけど聞くに値しない話だな」と判断する大人も一定数いてあげたほうがいいと思う。
そういう大人がいると、子どもは自分たちの世界の狭さに気づき、
「あれ、もしかして、俺らの考え方って駄目なの?」と、より広い世界に目を向けるきっかけになる。
そういえば、徳川家康が残した言葉というか、言ったとされている言葉に、
「人の一生は重荷を負うて遠き道を行くがごとし」ってのがあるけど、
落語家を始めとした芸を磨く人たちは、抱えている荷物が重くても重くなくても、歩かないことには「遠き道」を進めないわけだから、しゃべったり議論なんかしてないで、とりあえず日々、一歩でも歩を前に進めろって考え方をする。
「しゃべり」を生業とする談志師匠からしたら、芸につながらない子どもたちの「議論」はただの「だべり」に思えたことでしょう。
子ども(とかつての自分)がしゃべりたい、議論したいと思うのは、外の世界と自分の世界をなんとかつなぎたいと思っているからでもある。
しかし、同時に、自分の世界が狭く、脆弱であることもわかっているので、自分の感性と語彙で作った世界をどこかで破壊したい気持ちもある。
その点、談志師匠は最高の破壊者であったろう。
談志の無言での退室は、子どもの狭い世界を破壊する。
「子どもの話を聞かないこと」や「何も言ってくれないこと」が反転して、「教育」的であることも時にはある。