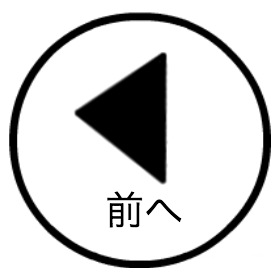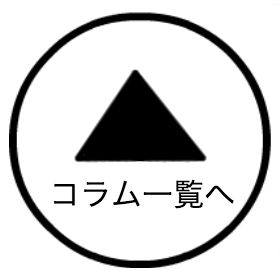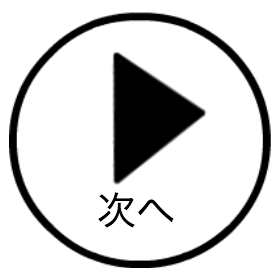京都はもしかするとクリスマス後進国なのかもしれない。
そう思わされるくらい、京都では街に出ても、クリスマスを感じることがない。
いや、もしかすると、それは街のせいではなく、新型コロナなどで、日本全体が、クリスマスにあまり踊らなくなってしまっているのかもしれない。
以前は、もっと、街で、クリスマスソングが流れていた気がするが、それはまったくの勘違いで、ただ自分が街にでなくなっているというだけなのかもしれない。
街で流れるクリスマスソングといえば、洋楽・邦楽どちらも定番曲があるものだが、本場イギリスでの定番・クリスマスソングといえば、ザ・ポーグスとカースティ・マッコールによる「Fairytale of New York(ニューヨークの夢)」が真っ先に挙がる。
この歌は、アイルランドからニューヨークに出てきた男女が一時は夢を掴むが、年老いて、お互いを罵り合うようになりながらもクリスマスを祝うといった内容の曲で、イギリスで最も人気のあるクリスマスソングに選ばれることもある。
これを歌っているザ・ポーグスというバンドがパンクバンドだったこともあり、この曲で使われる歌詞には、“Scumbag(いやらしい奴)”“Maggot(うじ虫)”“Faggot(オカマ)”“Slut(尻軽女)”など、とても上品な言葉が並ぶ。
このことで、イギリスでは、毎年のようにコンプライアンス問題が立ち上がっているようだが、今も現地の人々は、この曲を変わらず愛しているようである。
彼らは、「恋人たちのクリスマス」を歌うマライヤ・キャリーや、「ハッピー・クリスマス」を歌うジョン・レノンよりも、「淫乱ババア」「不潔なオカマ」と罵り合う移民を歌うザ・ポーグスを好んで聴いている。
それは、西洋人にとって、クリスマスが、夢破れた移民のような社会的立場の低い人々にも平等に訪れるハレの日であり、そこで歌われる主人公として、口の悪い移民は適格なのだと感じるからであろう。
現在も子どもたちにとってクリスマスが、夢と贈り物をもらえる日であるように、クリスマスは、何も持たざる者たちにこそ訪れる祝祭の日である。
そう思えばこそ、クリスマスは「恋人たち」のためにあるのではなく、「夢破れた移民たち」のためにある日である。
それでこその「ハッピー・クリスマス(john & Yoko)」である!
ザ・ポーグスはアイルランドにルーツを持つイギリス人なのだが、クリスマスは歴史的に4、5世紀ごろ、つまり、キリスト教がまだ完全に今の形になる前に、北欧やケルト(アイルランド)の冬至の祭と習合したことで完成したと言われる。
つまり、イギリス人が「Fairytale of New York(ニューヨークの夢)」を聴く時、そこには、歌い手であるアイルランド系パンクバンドの姿だけでなく、キリスト教がクリスマスを採用する以前のケルトのクリスマス(北欧でいうところのユール祭)が、想起されているのかもしれない。
クリスマスの語源である聖ニコラウスや聖ルチアを祝うようになる前、一年で最も暗い日が過ぎ去ったことをただただ祝った当時の祭には、下品な言葉を使いながらも冬至の訪れを祝った人々がたくさんいたことだろう。
イギリス人は今も「Fairytale of New York」を聞きながら、そうした「普通の人々」のクリスマスを祝っている。
キリスト教という裏打ちなしでクリスマスという祝祭イベントを頂戴した日本では、そうしたルーツを辿れるようなクリスマスソングはない。
恋人専用イベントとしてのクリスマスに、「きっと君は来〜な〜い」と嘆くか、「恋人がサンタクロ〜ス」とはしゃぐかくらいしかない。
クリスマスにやれることも、フライドチキンチェーン店でチキンを買って、コンビニでケーキを予約するくらいしかなく、12月25日だからといって、「メリークリスマス」と口々に、幸いなる日の喜びを見知らぬ人々と分け合えるわけではない。
知らない人同士であっても、その壁を超えて思いをもやうことができるのがクリスマスであり、この街にも、思いを分け合いたい人々はいるが、キリスト教という建前のないこの国では、思いを伝えることは容易いことではない。
本当は、普段は言葉を交わさない路上で寝ている人にも「メリークリスマス」なのである。
本当は、コンビニのイートインで菓子パンを食べているおばさんにも、「メリークリスマス」と言うべきなのである。
本当は、息が白くなるような寒空の下で交通整理をやっている外国人にも、ワンカップ大関ひっかけながら競馬新聞とにらめっこしている酔っぱらいにも、夜がとっぷりと更けてから駅に向かう風俗嬢にも、カーテン越しの巨体のドラッグクイーンにも、両親が怒鳴り合っている家に帰る中学生にも、訴訟の書類の中で眠る会社の社長にも、義母のおしめを買う契約社員の女性にも、バイトを掛け持ちしている専門学生にも、裸足で駅前に立っている虚無僧にも、似合わないクリスマスの帽子をかぶらされているスーパーの店員にも、ケンタッキーの前でプラカードを持ってるヴィーガンの群れにも、コンビニの裏をうろつく猫の親子にも、ゴミ袋をついばんでいる真っ黒なカラスにも、皆に平等に訪れる福音として、皆が共に享受できる慰めとしての、誰にも等しい「メリークリスマス」を言うべきなのである。
そうであればこその「聖なる夜」なのである。
この社会に、そうは言えない事情があるのなら、せめて、街中で、夢破れた移民を歌う「Fairytale of New York」くらいは流しておいてほしいのである。