
「お茶」の世界では、10年続けていても、まだ若手扱いされる。
40年、50年とやっている人がザラにいるからだ。
50年やっているおばあさんなんかはさすがに腰が曲がっていて、
「そんなに長く、お茶を続けられて、すごいですねえ」
なんて、周りに声をかけられている。
そうおばあさんに言う人たちは、本当にすごいと思っているのか、
ただのおべんちゃらで言っているのかは、よくわからない。
なんといっても、お茶の席での会話だ。
真実は表に出てこない。
哲学者や数学者の中には、30年、40年と、
同じルーティーンを繰り返しながら生きている人も多い。
毎日同じ道を通り、同じものを食べ、同じ量の日記を書く。
そうやって同じことを繰り返していると、いつもとは違う、
小さな違いに気づくようになる。
それは自然や現象の中に見いだす(小さな)変化の場合もあるし、
それを見いだした自分の中に感じる(小さな)変化の場合もある。
ずっと「同じ」を続けていないと、
小さな「違い」には気づかない。
それは、たぶん、「お茶」でも同じで、
抹茶をお湯で撹拌するだけの作業を、永遠と50年間繰り返すことでしか気づかない
「違い」というものがあるのだろう。
ただ、解剖学者の養老先生は、以前の日本人の考え方として、
「昔の人は、30年、40年、同じ仕事をやり続けている職人がすごいんじゃなくて、
30年、40年やり続けられる仕事の方がすごいのだと思っていた」
と言って、今との見方の違いを指摘していた。
すごいのは、続ける人ではなく、続けさせられる仕事の方。
価値があるのは、繰り返せる人ではなく、繰り返させられる仕事の方。
偉いのは、哲学であり、数学であり、「お茶」。
だから、本当は、
50年間お茶を続けているおばあさんを褒めるのではなく、
50年やっても全然飽きのこないお茶のディープさを褒めるべきなのだ。
「こんなに長く、続けさせられて、お茶ってのはすごいですねえ」
茶室にいる人たちはおべんちゃらを言うべき相手を間違えている。
本当に褒めるべきは、「腰の曲がったおばあさん」ではなく、
「腰の曲がったおばさんにも続けたいと思わせられるお茶」の方なのだ。

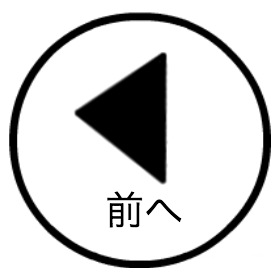
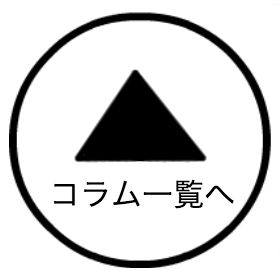
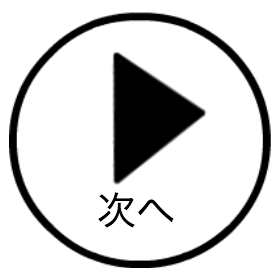
コメント